お電話
03-6300-0763
10:00~21:00(完全予約制)
2019.07.10

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
今月の21日、高田馬場で行われる(一社)北辰会の定例会で、久々に喋ります!!
(たった1時間ですが。(笑))
しかも今月の定例会には、藤本新風代表も見えます!!
代表講演のテーマは「経穴の考え方」。
しかも今回は、山梨の渡辺久子先生による特別講義「中医眼科学~基礎編~」もあります!!
実は、渡辺先生の御尊父は、山梨で有名な眼科医の先生なのです☆
聴き逃がせませんよ~~~(=゚ω゚)ノ
・・・で、今回私が喋るのは「十二皮部について」という、なかなか珍しいタイトルです。(笑)
この講義のスライドをまとめているんですが、ほぼ出来ました!!
・・・で、これをまとめる過程で、久々に『黄帝内経』の中と、その後の歴史における「三陰三陽学説」について勉強し直したんですが、これが楽しすぎる。。。(゚∀゚)
止まらなくなる。。。
時間忘れる。。。
『黄帝内経』の中では、素問の陰陽離合論、陰陽類論篇、霊枢の根結篇から、三陰三陽の開闔枢理論てやつをいじくり回して、六経弁証と重ねてみたり、
素問の皮部論と重ねてみたりしてたら、妄想が止まらない。。。
まあ、あまりマニアックな内容になっては上手くないので、初学者にも分かりやすく、この医学における「皮膚」の重要性を説こうと思います!!
乞うご期待!!!
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.06.05
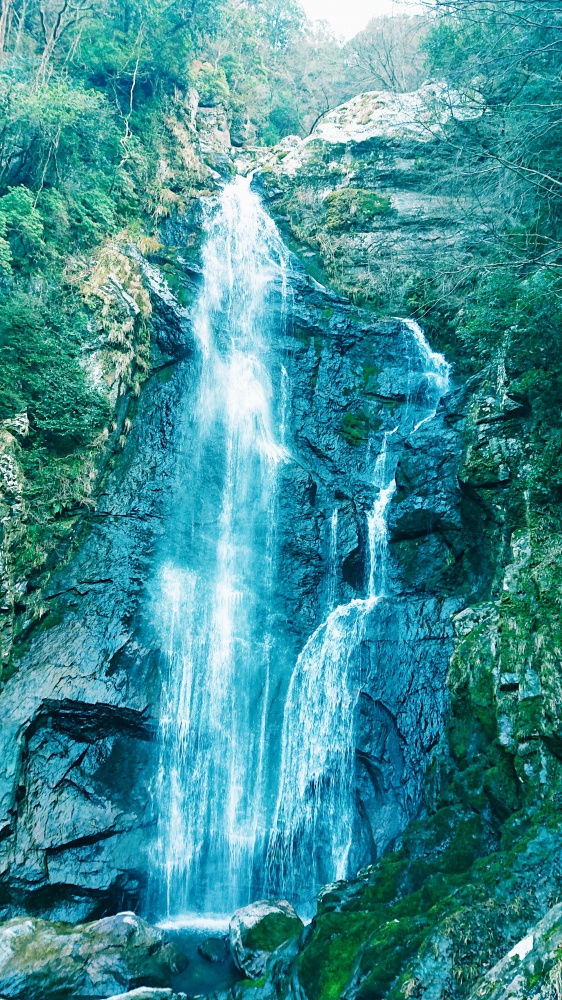
清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
こないだ読んでた本にたまたま出てきた、「扁鵲(へんじゃく)の六不治」。
・・・まあ「六不治」は、相当有名な話であり、この医学を勉強し始めた頃ぐらいから知ってはいたが、今読むと、また味わいが違う。(笑)
このブログでは、ずいぶん前にチラッと部分的に紹介しただけなので、いい機会なんで、ここらできちんと書いておこう。
あくまで「ご提案」 参照
↑↑なんか、上記の過去記事読むと、開業したてで漸く軌道に乗ってきたころで、患者さんを何としても治そうと意気込んで、よく言えば躍起になっている、
悪く言えば少し傲慢になっている、実に青臭い文章で、読んでて赤面しますね。(笑)
・・・でもいいです、そういう時期があって、今がある。
それも歴史の真実なので、別に修正とかしません。
「六不治」は前漢の司馬遷の『史記』扁鵲倉公列伝に出てくる言葉で、ここでいう「不治」というのは”治らない人”という意味ではなく、「医者から見て治しにくい人」という意味にとるのが妥当のようです。
・・・で、「六不治」の内容とは、
1.驕恣(きょうし)理を論ぜざるは、一の不治なり
(わがままでおごり高ぶり、論理的に物事を考えることが出来ない人)
2.身を軽んじ財を重んずるは、二の不治なり
(体よりもお金、と、治療費をケチる人)
3.衣食適する能わざるは、三の不治なり
(衣食が適切でない、あるいは何らかの理由で適切に出来ない人)
4.陰陽并背、臓気定まらざるは、四の不治なり
(陰陽のバランスが極端に悪く、五臓の状態が極端に悪い人)
5.形つかれて服薬能わざるは、五の不治なり
(体が衰えて、薬も飲めない人)
6.巫を信じ医を信ぜざるは、六の不治なり
(宗教を過信し、医師、医療を信じない人)
とあります。
・・・上記6パターン、全て治療にあたったことがありますが、まあー、治しにくいですよね。。。(苦笑)
とはいえ、それでも逃げずに治療に向かう、説明を尽くす。
・・・で、最終的には患者さんの体だし、命だし、患者さん自身の人生だし、というところで、患者さんの意向は最大限尊重する、可能な限り寄り添う、
無茶はしない、というところが大事じゃないかな、と思っています。
自分が出来ることを最大限やらせていただく、という姿勢が大事だと思うんで、患者さんを診ていて、
「こんなんだから治らんのだ!」
とかは、別に今は思わないですね。。。(*‘∀‘)
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.05.31

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
患者さんに多い、「カチカチ病」。
僕が勝手に名付けてるだけですが。(笑)
職場でカチカチ。
家でもカチカチ。
運動しない。
温度、湿度変化に体をさらさない。
効きすぎている空調により、夏は寒いところで仕事して、冬は暑いところで仕事してる。
結果、カチカチ病。
アトピー、リウマチなどのアレルギー疾患、癌、眩暈、婦人科疾患、精神科疾患、ほとんどこれ。
鍼はカチカチをゆるめる道具。
しかし、むやみやたらに打ったんじゃ、余計カチカチ。(゚∀゚)
どこまでゆるめるか、あえてゆるめ過ぎないか。
今日は泣く患者さんが多かった。。。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.05.06

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************
![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話し
◆順天堂の歴史を踏まえる。
かくして、12月に第一回目の講義に伺ってから、1月、2月、3月と、月に一回の講義に伺う中で、徐々に方向性やメンバーが定まってきて、4.25の大安吉日(たまたま)に、
順天堂大学医学部内に、小さいながらも大きな一歩、と期待できるような動きである「東洋医学研究会」が同好会として発足した訳ですが、2018年の秋頃に、
友岡先生から、この話が実現しそうだという電話が来た時、何となく御縁というか、妙な力を感じたんですね。
実は、私が開業してすぐの頃、大変お世話になった漢方家の先生(故人)の薬局名は「順天堂薬局」でした。
また、今から20年くらい前に、叔父が脳腫瘍で癲癇発作を起こし、倒れたことがあったのですが、その時入院、手術したのも、順天堂の静岡病院でした。
そのせいもあってか、何となく意味があるような気がして、順天堂の歴史に関して、今回色々調べました。
順天堂の歴史に関しては、公式HPに、非常に美しくまとめてくれてあります。
(メッチャカッコいいHPですよね。。。)
創立は1838年、長崎の出島にあった、あのドイツ人医師、シーボルトの「鳴滝塾」で三年間学んだ、佐藤泰然先生が、34歳の時に東京の薬研堀で、
母の姓である”和田”を冠して「和田塾」を開塾したのが始まりです。
その後、1843年に千葉の佐倉に移り、ここで初めて「順天堂」と名乗ります。
(因みに”順天”というのは”天の道理に順(したが)う”という意味であり、出典はなんとあの陰陽論の原典、『易経』だそうです。。。)
佐藤泰然の息子である松本良順は、あの緒方洪庵(1810-1863)が務めていた幕府の西洋医学所の頭取を務めた、かの新選組の主治医として知られる人物であり、
泰然の養子である佐藤尚中は大学東校(現東大医学部)の初代校長となり、その佐藤尚中の養子である佐藤進は、日本発のドイツへの医学留学生です。
緒方洪庵という人物 参照
・・・まあ、あまり細かいことを書いても仕方ないですが、要は、幕末から明治の、東洋医学が事実上の廃止政策の憂き目に遭った時代の、日本の西洋医学化の旗振り役、
中枢中の中枢こそが、この順天堂大学医学部なのです。。。
開学以来180年、順天堂が日本の医療に与えた影響ははかり知れません。
因みに風水の考え方に「三元九運論」というのがあり、180年を1周期とし、60年ごとに
「上元・中元・下元」
と呼んで、それをさらに20年ごとに
「上元一運、上元二運・・・、」
と、9つ(九運)に分けて、地運(大地のエネルギー、平たく言えばそこで起こることの運勢)を予測するというものがあるんだそうです。
最初の60年(上元)でものごとが発生、発展し、次の60年(中元)でものごとが繁栄し、次の60年(下元)でものごとが衰退し、次の時代に入る、
という診方をするんだそうです。
日本の西洋医学を牽引してきた順天堂大学に、180年経って、(恐らく)初めて、東洋医学研究会が出来たことは、何か意味があるような気がしますね。
またこれ以外にも、個人的に鳥肌が立つようなことがありました。
続く
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.04.30

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
4.28の日曜日は、高田馬場で行われた(一社)北辰会定例会に参加してきました!!
今回は本部から山本克仁先生、足立尚哉先生もお見えになって、今年度のガイダンスを喋ってくださいました。
その後、尾崎真哉支部長から「北辰会と肝病」という講義。
五臓の中でも、「肝の臓」の治療を非常に重視する北辰会。
私も以前、「肝病はこう治す!」という論考を、有料メルマガ『あはきワールド』に投稿したことがあります。
現代日本人を治療する上で「肝の臓」に対する理解は非常に大事なことと思います。
・・・今回、支部長の講義はかなり爆裂していたようです。(笑)
午後は実技訓練「脈診・顔面気色診・舌診・取穴」。
今回は私の方でデモと解説を喋らせていただきました。
どれだけ伝わったか分かりませんが、まあ来月も同じテーマで実技訓練があるようですので、また訓練しに来ていただけたらと思います。(^^)
新年度一発目、参加人数も多く、飲み会も実に盛り上がっていましたね~☆
まあしかし、こうやって勢いのある時ほど、慎重に、繊細に。
陰陽論であります。
続く
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.04.21

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話し
「五行」のはたらき 2 参照
◆従革とは。
さて今日は、これも聞きなれない金の性質、「従革」を説明します。
「金は従革」と定義したのも、紀元前5世紀ごろの書とされる『書経(尚書)』の洪範です。
これは、中国隋代の蕭吉(しょうきつ)によって撰述された『五行大義』によれば、
「従」・・・範(のり)に従い
「革」・・・更(あらた)まる
という意味だそうで、金属が溶けて容器や刃物など、様々な形に姿を変えることからこの性質が言われるようになったそうです。
また、後漢の許慎の『説文解字』では、「金は禁」といわれ、金の時季である秋になると、自然界の陰気が盛んになりだし、万物の成長が止まる(ある意味で成熟する)、と説明します。
それを「粛殺の気」と言います。
これは、以前にも書いていますが、8月の立秋の頃になると、朝晩の空気、風に微妙に出てくる、あの感じのことです。
秋燥の気 参照
また「金」という漢字の中には「土」が隠れており、間にある「’ ’」は、金属が土の中で光っているさまを示す、と説明します。
「金」は方位(空間)では西方、季節では秋です。
西方は日が沈む方角、死の世界ですね。
しかしこれも大事な自然の摂理です。
天の道理に順う粛殺は、新しいものを生み、発展の方向に向かうのですが、天の道理に従わない粛殺は、かえって新しいものを生まなくなり、
衰退を招くという、重要な教えが含まれています。
「金」は臓腑経絡では肺の臓(手太陰肺経)と大腸の腑(手陽明大腸経)、経穴では陽経の井穴と陰経の経穴です。
肺・大腸 参照
臓腑では稼穡の土は脾胃で、従革の金たる肺大腸とはいわゆる相生関係にある訳ですが、これが経絡的には太陰経と陽明経で手足一対になっていることも興味深く、
流注の順序からしても肺→大腸→胃→脾と密接であり、陰陽ともに気血が旺盛(太陰と陽明)、というのも意味深いですね。
十二経の流れの順調度合いは、胃の気の充実(一つには稼穡力)からの肺金の従革力(死と再生)ありきな訳です。
また、金(従革力)に関与する経穴を実際に動かす時は上記のような考えを持つと、診どころが変わってくると思います。
例えばよく使う陽経の井穴刺絡とか、霊道穴とかね。(゚∀゚)
続く。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.04.17

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
今日は2019.4.17でございます!!
今日から5.5までが「春の土用」であります。
現在、二十四節気では「清明」節です。
(清明院の清明です。(^^))
「清明」の意味は「清浄明潔」であります!!
二十四節気をさらに3つに分けた七十二侯では、今は末侯の「虹始見(にじはじめてあらわる)」であります。
虹が始めてあらわるということは、梅雨に向かって空気が潤ってくることを示します。
・・・で、次の節は「穀雨」であります。
そして、土用が明けて、「穀雨」の次の節、5.6からがいよいよ「立夏」であります。
また、今年の穀雨~立夏は新元号である、「令和元年」でもあります。
春の終わりに潤った空気が、患者さんに何を起こすか、また、改元によって忙しくなる患者さんに、何が起こるか、GWの連休の過ごし方はどうするのか、
これらの諸問題をよくよく考えて、慎重に対処しないといけません。
土用で穀雨だから、空気が潤うから、イコール脾が弱るだの、イコール土克水で腎に来るだの、そういう短絡的発想はやめましょうね☆
やはり多面的観察が大事。
でも、時節も大事。
我々は、生物学的人間であると同時に、社会学的、文化的人間を診ているのであります。
蓮風先生や、『内経気象学』の橋本浩一先生も良く仰るが、東洋医学では、基本として運気や時節を鑑みつつも、常に実際の気候気象、風向や気温湿度、
その患者に起こった現象等々から、多面的観察の上で総合判断しなさいよ、という、重要な教えです。
陰陽論を、機械的に運用するという愚を犯してはならない。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.25

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話し
ここまで、『黄帝内経霊枢』九鍼十二原(1)に出てくる補瀉法のうち、補法に関して、先日のセミナーで藤本新風先生が強調しておられたやり方に関して書いてきました。
しかし、補法だけへの理解ではアンバランスです。
今日はこの部分に書かれている瀉法についても書いておきます。
しかもしかも、誤解を恐れず言うと、現代日本の鍼灸院での外来臨床では、運動不足で飽食の時代、デスクワーク中心の頭脳労働、ストレス社会、
結果的に癌、脳卒中、心臓病、糖尿病など、あらゆる邪気(病理産物)をため込んだ、実証(邪気のカタマリ)の患者さんが、基本的には多いように思います。
(苦笑・・・もちろん決めつけはダメですが)
ですので、瀉法に対する理解、適切な運用は非常に重要です。
瀉法の場合は素早く刺入してゆっくりと抜く、「速刺徐抜」です。
(因みに補法はその逆ね。「徐刺速抜」です。)
しかも鍼孔は閉じず、邪気を漏らせと書いてあります。
ここに、抜鍼の時に「排陽得鍼(陽を排して鍼を得べし)」という表現が出てきます。
これには色んな解釈があるようなのですが、要するにきれいに邪気を散らすためには、皮膚表面の気を停滞させないことです。
瀉法の場合、グッと一気に刺鍼して、ジワーッと抜く、しかも皮膚表面に気を停滞させずに、きれいに邪気が散るように持っていく、これが大事です。
ただ、邪気であれ正気であれ、どちらも所詮は「気」です。
補瀉の対象は「気」。
ここには「言実与虚.若有若無.(虚と実を言わば、有るが如く無きが如し)」と書いてあります。
補瀉とは、相対的なものであるということです。
新風先生も、先日の講義の中で石坂宗哲(1770-1841)の補瀉観である「虚法、実法」を紹介していましたが、ここらへんが補瀉の妙だと思います。
まずは型を覚え、しかる後に、それを臨機応変、変幻自在に運用できる世界を志向する。
型が大事、基礎が大事、でもそれにとらわれないことが大事。
それまた陰陽論。
おもしれ-話になってきたけど、おわり。(゚∀゚)
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.20

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
二十四節気、明日はいよいよ春分です!!
しかも明日は満月です!!!
そんな訳で、今日は督脈大活躍。
至陽、八椎下、脊中などなど。。。
どれも、大変素晴らしい想像を与えてくれますね。
・・・ただ、患者さんによっては滋陰、補血、温補腎陽なんかも、かなり炸裂してましたね。
ここら辺のシャープさを、もっとシビアにしないと。
陰陽、今日も動いております!!
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.15

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
数千年前の外国の話なんで、ホントかどうかは専門家に委ねるが、『黄帝内経』よりも以前は、シャーマン(巫師、祈祷師、巫医)による祝由(しゅくゆう:おまじない)がメインだったという。
(丸山敏秋『黄帝内経と中国古代医学』東京美術 など参照)
それが、『黄帝内経』に至って、「気と陰陽」という当時としては最新の認識論(哲学)でもって、ある意味それまでの医術が「科学化」され、
現在まで脈々と続いているのが東洋医学だという。
『黄帝内経』を読んでみると、鬼神の話や、死後の世界、前世の話などは、意図的と思えるほど、論じていない。
(その割には”魂魄”なんていう考え方は出てくるが。。。)
我々、現代の鍼灸師が学校で教わる、360以上の経穴の中にも、「鬼」の文字がつく経穴はない。
しかし、鬼神による病理説を重んじていた時代の名残なのか、あるいは『黄帝内経』以降も、鬼神をイメージして経穴を使う医師がいたからなのか、
”別名”として、「鬼」の文字を使う経穴が存在する。
経穴名に「鬼」を入れるということは、少なからず「鬼」による病理を射程に入れた治療を行っていたのであろう。
有名なのは中国唐代の名医、孫思邈(581?-682)大先生の『千金翼方』の中に出てくる、「孫真人十三鬼穴」だ。
孫思邈という人物 参照
今は便利な時代で、ネットで検索すればすぐに13穴出てくるので、あえて全部は書かないが、我々がよく使う
申脈穴に「鬼路」、曲池穴に「鬼腿」
という別名があるのは興味深い。
因みに、「孫真人十三穴」に入らないものもあり、臨床であまり使わないものもあるが、
湧泉には「鬼井」、人中には「鬼宮」、大陵には「鬼心」、間使には「鬼営(鬼路と書いてある本もアリ)」
という別名がある。
・・・今日、先輩とのやり取りの中で、「間使」の話題が出た。
「間使」は”密行の使者”という解釈があったり、”外関の別絡と通じ、鬼神がこの間を遊行するが如き・・”と言われます。
と、いうことは・・・??
・・・はーおもしれ。(゚∀゚)
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.07.08
2016.05.09
2016.04.12
2016.04.28
2015.06.04
2012.12.23
2014.02.17
2014.04.26
2025.12.12
患者さんの声(睡眠障害、その他不定愁訴)2025.12.05
2025年11月の活動記録2025.12.01
2025年 12月の診療日時2025.11.22
患者さんの声(15年以上メンテナンスで継続通院)2025.11.20
11.22(土)、25(火)、通常通り診療やります!!2025.11.19
2025年10月の活動記録2025.10.29
2025年 11月の診療日時2025.10.15
2025年9月の活動記録2025.10.10
清明院16周年!!!2025.10.01
2025年 10月の診療日時2025.09.20
2025年8月の活動記録2025.09.01
2025年 9月の診療日時2025.08.15
2025年7月の活動記録2025.08.01
2025年 8月の診療日時2025.07.04
2025年6月の活動記録2025.07.01
2025年 7月の診療日時2025.06.26
2025年5月の活動記録2025.06.01
2025年 6月の診療日時2025.05.10
2025年4月の活動記録2025.05.01
2025年 5月の診療日時2025.04.04
2025年3月の活動記録2025.04.01
2025年 4月の診療日時2025.03.13
2025年2月の活動記録2025.03.01
2025年 3月の診療日時2025.02.06
2025年1月の活動記録2025.02.01
2025年 2月の診療日時2025.01.21
順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10
2024年12月の活動記録2025.01.02
2025年 1月の診療日時2025.01.01
謹賀鍼年!!2024.12.28
年内診療終了!!2024.12.14
2024年11月の活動記録2024.12.01
2024年 12月の診療日時2024.11.07
2024年10月の活動記録2024.11.01
2024年 11月の診療日時2024.10.10
清明院15周年!!!2024.10.09
2024年9月の活動記録2024.10.01
2024年 10月の診療日時2024.09.19
2024年8月の活動記録2024.09.01
2024年 9月の診療日時2024.08.03
2024年7月の活動記録2024.08.01
2024年 8月の診療日時2024.07.10
患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05
2024年6月の活動記録2024.07.01
2024年 7月の診療日時2024.06.05
2024年5月の活動記録2024.06.01
2024年 6月の診療日時2024.05.10
2024年4月の活動記録2024.05.01
2024年 5月の診療日時2024.04.13
(一社)北辰会、組織再編。