お電話
03-6300-0763
10:00~21:00(完全予約制)
2012.09.19
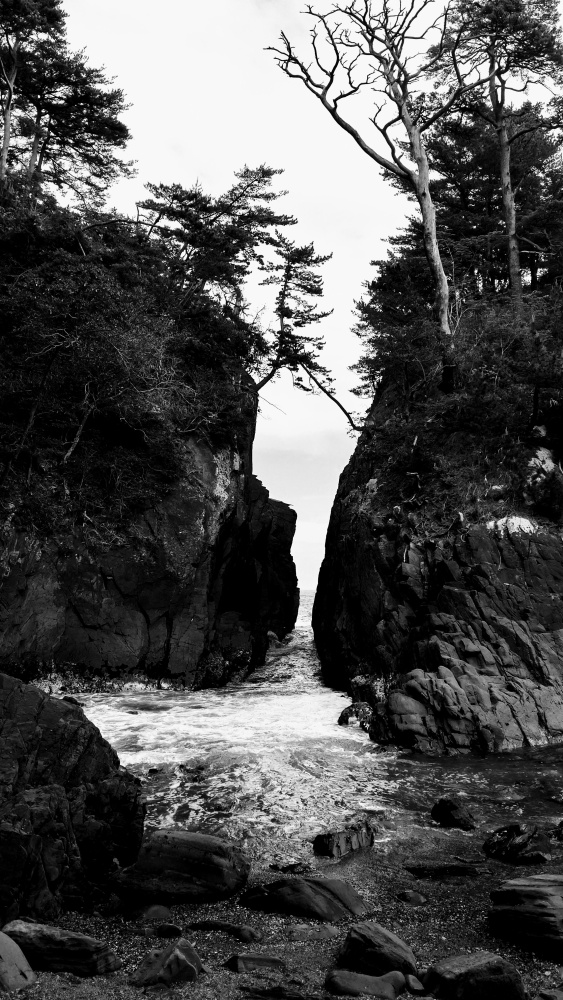
清明院では現在、求人募集しております。
本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?
募集内容の詳細はこちら。
**********************************************************************************************
![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
昨日の話に出てきた、何やら難しそうな「決定論(けっていろん)」という言葉・・・。
『荘子』の渾沌のお話 参照
な~んか、難しそうな言葉ですよね。
こないだ読んでた本にも、何度か出てきまして、気になったのでちょっと調べました。
ヤフー百科事典によると、
常識的には、未来の事柄のなかには、人間の自由意志によって、それが生ずるかどうかが左右されるものがあり、
この意味で未来には不定な部分がある。
この常識に逆らって、世の中でどういうことが起こるかは、未来永劫(えいごう)にわたってすべてあらかじめ決定されている、
と主張する立場が、決定論である。
とあります。
・・・相変わらず、辞書や百科事典っちゅーのは、分かりにくい言い回しですな。。。
でもこれはまあ、分からんことはないですネ。(苦笑)
要するに、未来に何が起こるかは、あらかじめ分かっている!とする立場が決定論なんですね。
これをネットなんかで検索すると、とんでもなく難しい(というか眠くなる)哲学のサイトにたどりついたりして、眠れない夜には最高です。(爆)
睡眠薬よりよく効くんじゃないでしょうか。(睡眠薬飲んだことないけど。)
〇
・・・ま、決定論は、パッと聞き、”んなわきゃねーだろ!”とも思える話です。(笑)
でもこれを深く考えると、なかなか難しい話になっていって、宗教、哲学、道徳、神学、物理学や自然科学の分野なんかでも登場してくる、重要な考え方です。
ここではあまり深い内容には立ち入りませんが(というか難しくって無理ですが(苦笑))、全てがあらかじめ決まっているだなんて、なんだか面白くない話ですよね。
・・・「因果律(いんがりつ)」という言葉がありますが、原因があって、結果がある、ということが正しいならば、その原因が成立するにも、また原因がある、ということになり、
ある結果が起こった原因も、その前に起こった原因の結果である、と考えると、いくらでも遡ることが出来るので、逆に言うと、今が決まってるなら、
未来に関しても全てが決まっている、とも考えられます。
これ、ややこしーけど、分かるっしょ?
これを”因果的決定論”というらしいです。
この考え方は、何かを予測する時、普段から誰でもある程度は使いますが、なんぼ予測しても、予定は未定、”100%決定”ではないですよね。
僕的には、世の中、一寸先が分からないから面白いんだと思います。
不思議な力を感じることはありつつも。
1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.09.06
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
タバコと東洋医学
タバコと東洋医学(その2)
タバコと東洋医学(その3)
タバコと東洋医学(その4)
タバコと東洋医学(その5)
タバコと東洋医学(その6)
では、続きいきます!!
前回、禁煙した時に僕自身の身に起こった、様々な症状について書きました。
・・・で、なぜ、それらの症状が起こったのか、というお話です。
1.イライラ感
これについては、「肝の臓」のところでよく出てきましたが、伸び伸びとした自由な状態を好む「肝の臓」が、タバコという嗜好品を奪われたことにより、
欲求不満がたまって、機能失調を起こしたことが、一番大きいと思います。
肝の臓が機能失調を起こすと「易怒(いど)」といって、些細なことで怒りっぽくなったり、イライラしたりするようになります。
2.のぼせ感、頭に汗が出る、鼻血
コレは、タバコによって、深い呼吸をすることで、無理やり下げていた気が、下げられなくなったことによって、上半身に気が鬱滞して、
熱をこもらせ、これらの症状が出たものだと思います。
3.口内炎の多発
これも、2.と同じように、上半身(上焦)に気が鬱滞し、熱がこもった結果であろうと思います。
現代医学的には、唾液に含まれる抗菌物質の濃度が、喫煙者は煙の毒で刺激されるせいか、非喫煙者よりも高いようで、
このせいで口内炎が出来にくいという説もあるようです。
この論から言えば、煙を肺まで入れないのであれば、タバコはむしろ健康にいい、とも取れますが、この論には異論もあるようです。
4.痰が絡む
タバコをやめて、余計に痰が絡むなんて、信じられないようですが、ホントの話です。
実際に経験した人が言うんだから間違いない。苦笑
コレはタバコと東洋医学(その2)で述べた内容そのものです。
5.体重の増加
これについては、スススーッと、これまでにないペースで一気に増えてきたので、このまま80㎏、90㎏の、
メタボ中年のだらしない体になっていくんではないかと、正直焦りました。
人からは、タバコを吸えないストレスから、暴飲暴食になっているんじゃない?とか、よく言われましたが、僕はかつては、これを暴飲暴食と言わなかったら、
何を暴飲暴食というのか、という食生活でしたから、食生活自体は、以前よりも全然マシになっていると思います。
・・・にも関わらず、なぜ太るのか。
コレは、上記のように「肝の臓」の機能失調や、「痰」という邪気が助長されたことで、結果的に消化吸収機能が煙草をやめる前よりも、
うまく働かなくなった結果だと思います。
ですので、鍼灸と養生で、「肝の臓」を調整しつつ、「痰」や「のぼせ」を根気よく除去していくことで、徐々に徐々に普通の状態に戻ってきた、という印象です。
(これ正直、2年近くかかりました・・・。)
・・・まあこのように、長く続けてきたことを急にやめたら、色んなことが起こるというのは、タバコに限らず、よくある話です。
よく、痛み止めやステロイドで、何年も症状をごまかし続けていた患者さんが、一念発起して、急に廃薬しようとすると、一気に色んな症状が噴出することがありますが、
それと似たような現象なのかもしれません。
でも、その辛いリバウンドを乗り越えることが出来れば、次に進めるワケですから、やってみた方がいいとは思います。
タバコと東洋医学、ひとまず終わり。
これについてはまだ色々あるので、また気が向いたら、書き足すかもしれません♪
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.08.22
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
では、続きいきます!!
僕がタバコをやめた時のお話に行く前に、タバコの「プラス面」について、少し補足しておきます。
前回お話ししたように、タバコには、
「胸部~上気道部に絡んだ”痰”という邪気を乾かす。」
という、いい面もある、というお話をしました。
(もちろん、痰をため込んでいる人にとっては、対症療法的に、症状緩和という意味で、ですよ。)
これにより、人によってはリラックス効果はもちろん、呼吸器症状がかえって楽になったり、息苦しさがかえってマシになったりする人が、実際にいます。
では、タバコが持つ「いい面」というのはそれだけであって、他にいい面はないのでしょうか。
・・・「ある」と思います。
近年、まるで「諸悪の根源」みたいにしか言われないタバコですが、もとはナス科の植物の葉っぱを乾燥させたものに、火を付けたものです。
煙草の歴史については 「JT」のHP 参照
葉の成分であるニコチンには、確かに毒性があるけれども、なぜ長い間、嗜好品として支持されてきたんでしょうか。
それには、それなりの理由があるはずです。
ここは冷静に、多面的に評価するべきでしょう。
それはあの匂いと、深呼吸(ため息と言ってもいい)によるリラックス効果が大きいのではないでしょうか。
こんなこと言うと、ヒステリックな嫌煙家の皆様からは、
「アレがいい匂いだなんてとんでもない!!どうかしてる!!」
と言われそうですが(苦笑)、僕も10年以上タバコを吸っていた身です。
タバコによって、いい匂いと感じる匂いや、自分に合う匂い、合わない匂い、というのは、厳然として存在します。
だからあれだけ多くの銘柄が存在するのだと思います。
・・・まあ、コレは吸ったことのない人にはいくら言っても分からないと思いますがネ。(苦笑)
その人の主観によりますが、「いい匂い」だと、その人が感じる香りには、気の巡りをよくし、脾の臓の働きを鼓舞し、湿邪を化する効果があります。
これを中医学の専門用語では、芳香理気(ほうこうりき)、芳香化湿(ほうこうけしつ)、芳香醒脾(ほうこうせいひ)なんて言葉があります。
ちなみに漢方薬においても、生薬の匂い、香りというのは大変重要なんだそうで、専門家の先生に伺うと、同じ材料であっても、きちんとした、
素材本来の香りがあるかどうかで、効果が全然違うらしいです。
また、重症で、意識不明になったような患者さんを、キツイ匂いのある生薬を嗅がせて、意識を付けるという、芳香開竅(ほうこうかいきょう)という方法もあります。
(韓国ドラマ『イ・ジェマ』でよく出てきましたね。)
また、深呼吸や、ため息というのは、東洋医学では特別に考えます。
そもそも、「呼吸」というものに対する考え方が、東洋医学と西洋医学とでは違います。
長くなりそうなんで、次回。
・・・こうやって、一つの話題から派生して、細かいことに触れていくと、どんどん長くなってしまいますが、それがこのブログの自由さ。
竹下式。(笑)
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.08.21
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
前回のお話・・・
では、続きいきます!!
タバコ(煙草)については、いくつかの日本の江戸時代の名医達の医書にも出てくるようですが、ここでも意見は分かれています。
☆煙草なんて、メマイはするし、金はかかるし、火事のもとにもなるし、やめた方がいいよ!
(by 貝原益軒 『養生訓』)
☆いやいや、煙草は、胸の痞え感とか、痰がとれて気の流れがよくなるし、冷えや余分な水分によるシビレの病気にはイイよ!だけど熱がこもるから、老人はやめた方がいいな~。
(by 香月牛山 『老人必用養草』)
☆大して害がないから、別にやめさすこと無いよ。あんまり咳や痰が出てる時は控えさせりゃいいってぐらいカナ。
(by 平野重誠 『病家須知』)
・・・だそうです。
この記載、下記のブログ様を参考に引用させていただきました。↓↓
http://blog.goo.ne.jp/harumi4567/e/361bcee05abaf1382eb402b06b734fad
まあ、東洋医学的にも、見解の分かれるところだ、ということでしょう。
この中で、香月先生の、「痰がとれる」という言い方に、違和感を感じる人が多いのではないでしょうか。
(「痰」については「痰(たん)」「瘀血(おけつ)」について 参照)
「煙」という異物(汚れた空気)が気道に入るんだから、軽い炎症を起こして、痰がかえって絡むはず、と考えるのが普通でしょう。
でも実際は違うみたいです。
「煙」というものは、基本的に何かが燃えたから発生するものであり、五行で言えば「火」、陰陽で言えば「陽」の性質を持っています。
(もちろんその毒性は、燃やされたものによって異なりますが。)
つまり陰の性質を持った邪気である「痰」は、”さほど有害でない”タバコの煙の陽気によって、ある一定、乾かされる側面があるのです。
つまり食生活の不摂生や胃腸の弱り等によって、「痰」という邪気を体にため込んでしまっている人にとっては、
タバコを吸っていた方が症状も出ず、楽にいられるという側面があるのです。
(毒を以て毒を制すじゃないけど)
また、お香や、お灸の煙などは、匂いにリラックス効果があり、むしろ有益、とされています。
煙というのは、もちろんモノによりますが、「過度でなければ」問題ないのです。
(一社)北辰会でも、患者さんでヘビースモーカーの人には、無理にやめろとは強制しないように、と教わったことがあります。
煙草を吸うことで取れているバランスを一気に崩してしまい、思わぬ症状が出る場合があるからですね。
まるで強い薬を断薬する時と似ていますね。
・・・で、僕自身、急にやめたらエライ目に遭いました。(苦笑)
次回はそのお話。
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.08.08

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
乳製品は体にいい?
乳製品は体にいい?(その2)
乳製品は体にいい?(その3)
乳製品は体にいい?(その4)
乳製品は体にいい?(その5)
では、どんどんいきます!
今日はいよいよ、ムスタファさんからご質問の、コーヒーについてです。
ご質問の内容は、
1.コーヒーの寒熱がよく分からない。
2.ロースト(焙煎)すると寒熱が変化するのか。
とのことでした。
これについて考えてみました。
1.については、コーヒーは四気五味説で言うと四気は「温」、五味は「甘・苦」です。(メディカルユーコン『東方栄養新書』参照)
すなわち、コーヒーそのものについては、
「熱」というほどではないけど、どちらかというと温める方向に作用する
と、東洋医学では考えております。
2.については、乳製品の「酸化」の話の中でも述べましたが、変化すると思います。
コーヒーに限らず、「食品」というのは、熱を加えたり、冷やしたり、発酵させてみたり、味付けや食べ合わせによって、複雑で微妙に寒熱温涼などの陰陽バランスが変化するものだと思いますし、
しかも最終的にはそれ単品ではなく、様々な食材を実に複雑に組み合わせた「料理」という形で、しかも固形物やりゅう動物なども相まって体に入るワケですし、しかも料理も単品ではないですし、朝昼晩でも品目が違います。
超複雑系であり、ある一品について考察しても、それだけを摂って生きているわけではないので、極端に大量摂取でもしていないのであれば、いきおい、考察する意味自体あるのか??という気すらしてきます。苦笑
さらに現代においては、恐ろしいことに加工食品や添加物まみれの形で体内に入ってきますから、それぞれの食品(原材料)が持っている四気五味が、必ずしも絶対的な指標になるとも限らないと思います。
毎日、実に色々なものを口に入れてる中で、ある食材一品のみ捕まえて、
「東洋医学的には四気五味説で〇〇だ」
といっても、実際はその組み合わせのパターンは無限にある訳です。
ですので、まずはその人のもともとの体質を的確に分析し、さらに、その食生活や嗜好品を摂るようになってから具体的に何が起こったのか、
という結果から、慎重に帰納してみないと何とも言えない面もある、なかなか難しい問題です。
コーヒーについても、もともとは豆なわけですが、その豆を乾燥させ、さらに熱を加えて、煎った状態から、さらに煮出す、という飲み物なので、ある意味、もともとの豆をかなり陽性に傾けたものを使っていると考えられるので、
四気では結果的に「温」と解釈するんだと思いますが、コレがキンキンに冷えたアイスコーヒーなのか、砂糖を入れるのかミルクを入れるのかで、当然変わってきますし、豆そのものの焙煎の程度によっても変わってくるでしょう。
(いわゆる、”深煎り”か”浅煎り”かの問題ね。)
清明院の問診でも、「嗜好品がコーヒーです。」と患者さんがおっしゃった場合でも、1日何杯くらい飲むかはもちろん、それは夏冬問わずにアイスなのかホットなのか、
ブラックなのか加糖なのか、ミルク入れるのか、飲むとどのような反応が得られるのか(ホッとするのか、シャキッとするのか、症状に変化はあるのか)等々、
細かく絞り込んだ上で臨機応変に考えます。
ここに、ただ単に、”嗜好品がコーヒー”とか、”コーヒーは飲めない”というだけの問診情報では、東洋医学的な診断意義はあまり持たない、ということを付け加えておきます。
〇
まあ、もともとはアフリカやブラジルを中心とした暑い国で出来た「豆」ですから、コーヒー豆をもし生で食べれば、冷やす方向に働いても全然おかしくないと思います。
まあ、生のコーヒー豆は食べたことないし、流通も一般人にはほとんどしていないと思いますがネ。(苦笑)
「焙煎」という方法を使って陽性に傾けることで、世界中を魅了する、あの独特の苦みと香り、渋みが得られるのです。
(因みに中国ではお茶と比較するとあまり人気がないそうです。)
当然ながら、嗜好品として成立するには、栄養価や性質だけでなく、「味」や「香り」も、重要な要素なのです。
だからコーヒーは基本的には「温」性ですが、苦みの程度、渋みの程度によって、影響を与える臓腑も変わってくるでしょうから、繰り返しますが、通り一遍にこうと言えない部分がかなりあります。
それを踏まえた上で、知っとくといいかな、と思うのは、基本的には「豆類」というのは腎の臓を強くし、利尿作用があるものが多いので、
豆を食べた人の体の状態によって、結果として温めたり、冷やしたり、寒熱を調整してくれる効果が出る、ということです。
「腎」って何ですか?(その11)
「形象薬理」という考え方 参照
コーヒーについてはまだ色々あるんで、次回もう少し、補足します。
ムスタファさん、ご質問への回答としては、こんなところですが、いかがでしょうか??
何か分からないことがありましたら、またどうぞ。
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.08.03
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
昨日の記事に、ムスタファさんからご質問いただきましたので、僕なりの回答含め、何回かに分けて、ちょっと補足しようと思います。
乳製品は体にいい? 参照
ちょっと専門用語が出てきたりしてややこしいので、つまんない人は斜め読みして下さい。(笑)
・・・まず、乳製品は冷やす冷やす、と、なぜ東洋医学では言われるのか、という問題からいきます。
コレは、乳製品の過飲が、胃腸に負担をかけるから、結果的に消化力を落とし、他の飲食物の栄養吸収力が下がり、結果的にエネルギーが産生されにくくなったり、
老廃物が停滞したりする場合があるから、ということだろうと思います。
少し専門的な話ですが、東洋医学では「四気五味説(しきごみせつ)」と言って、自然界の飲食物を
”寒・熱・温・涼”の四気、
”酸・苦・甘・辛・鹹”の五味
に分けて考える学説があります。
(この学説についても、そのうち解説しましょう。)
あらゆる漢方薬や薬膳などの生薬、食品の配合も、基本的にはこの「四気五味説」に従います。
これで言うと、牛乳は東洋医学では
「乳ナイ(女+乃)」
と言われ、
四気では平(へい・・・つまり、寒熱どちらにも偏っていない)、
五味では甘、
臓腑では脾胃に主に関わる
とされ、
潤・降の作用がある
ことから、
陰虚や血虚、通便に効果あり
とされております。
ここだけ聞くと、色々なものに効く、魔法の飲み物のように思えますが、「潤・降」の作用が強いということは、逆に言えば陽気の働き(体を温め、清らかな気を昇らせる)を抑えてしまう側面も持っている、ということです。
つまり専門的には、あくまでもその人のキャパを超えて「過飲すると」の話ですが、牛乳は主に脾の臓の陽気を傷める側面がある、だから結果的に冷えるのだ~!
という論なんだと思います。
脾の臓については「脾」って何ですか?(その9) 参照
ちなみに牛乳については、現代医学的にも、現代栄養学的にも、
ガン予防、安眠作用、血圧降下作用、骨粗鬆症予防作用など
が謳われていますが、これについて辛辣な反論もある、というのは、前回書いた通りです。
〇
・・・まあただ、「過飲」という量の定義なんて、人によって違い過ぎるので、一概にこの量飲んだらいけません、なんて話は出来ませんし、
一切飲むな、というのも行き過ぎだと、個人的には思います。
そもそも「牛乳を飲む」という食文化が日本に入ってきたのは飛鳥時代以降だそうですが、最初は天皇や皇族のみが利用していたそうです。
一般庶民が飲むようになったのは明治以降、さらに、”アメリカンライフスタイル”なんつって爆発的に普及しまくったのは、戦後の話だそうです。
給食で出るようになったのも、戦後からです。
(・・・ここら辺が、一部の人の思想を大いに刺激して、偏った、感情論的であったり、謀略論的な論調がネットに溢れている一つの要因なんじゃないでしょうか。)
まあ確かに、明治政府や、戦後の日本政府が採用した栄養学の是非論については、僕も興味のあるところで、あれが果たして正しかったのか、
相当見直す必要があるのでは?とは思っています。
『伝統食の復権』(島田彰夫 東洋経済新報社 2000年)には、
「高脂肪・高タンパクを説くドイツ栄養学を無批判に受け入れた明治日本。
戦後は、アメリカの食糧戦略に基づいた食生活改善運動により、伝統的な食文化は否定され破壊された。
高度経済成長の影響もあり、今や日本は “飽食の時代” を迎えている。」
とあり、この指摘は、参考にする価値が高いと思います。
しかしながら、最近のアレルギーベイビ―の問題であったり、三大成人病の問題を、すべてこれのせい、と短絡的に結論付ける風潮も、
いかがなもんか、と思っていますが。
一番イカンのは、最初に無批判に受け入れたことと、時代が変わっても、それに合わせて変えようとしない姿勢だと思いますが。
・・・話が逸れた、次回に続きます。(笑)
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.07.29
2012.07.28
2012.07.21
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
最近、「膝に水がたまった人」を何人か診ました。
(意外とこういう、よくある感じの、普通の患者さんも診てますよ~。)
中高年の病気と思われがちですが、スポーツなどで膝に過度の負荷をかけている人なら、若い人でもなる場合があります。
整形外科では、膝関節の中のどの組織で炎症が起こっているのかを、様々な検査で明確にし、基本的には患部の安静を指示し、
やれ湿布やら電気治療やら薬やらで様子を見て、溜まっている水が減らなかったり、ますます増えてくるようなら、
穿刺廃液(プンクチオン)といって、太い針を刺して直接水を抜きます。
それでもだめなら、炎症を起こしている組織そのものを手術でとっちゃったり、人工関節にしたりします。
〇
ところで、この「お水」というのは、何らかの原因で、膝関節が炎症を起こして「余分な熱」を持ったから、ある意味でそれを冷やさんがために、
体の中の正常なお水が集まったものなので、もともとは悪いものではありませんし、そのお水をとることが、根本解決にはなりません。
だから、とってもとっても、すぐにまた溜まって、いわゆる
「クセになった。」
と言われるような状況に陥ったりします。
しかし、かつて僕が整形外科で働いていた時、この、とったお水を見せてもらったことがあるのですが、黄色っぽくて、
場合によっては血が混じってたりして、とても「普通のお水」とは思えない、見るからに汚らしいものでした。
この「お水」をとってもらった患者さんは、いかにも病的な成分をとってもらったという感じで、違和感が取れてスッキリするらしく、晴れ晴れとしたお顔でお礼を述べて帰っていかれました。
(・・・まあ、またすぐに来るんだけどネ。(苦笑))
つまり、冷やそうと思って集まった綺麗なお水も、原因が改善しないために、だんだんだんだん薄汚れて、濁ってきて、「汚水」となり、コレ自体が痛みや違和感を増強させる要因にもなってしまうんです。
この悪循環から抜け出すのに、東洋医学の考え方が、とっても有効です。
長くなっちゃった・・・。
続く
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.07.18
2012.07.08
2016.05.09
2016.04.12
2016.04.28
2015.06.04
2012.12.23
2014.02.17
2014.04.26
2026.02.01
2026年 2月の診療日時2026.01.29
2025年12月の活動記録2026.01.06
2026年 1月の診療日時2026.01.01
2026「丙午」謹賀鍼年!!!2025.12.30
年内診療終了!!2025.12.12
患者さんの声(睡眠障害、その他不定愁訴)2025.12.05
2025年11月の活動記録2025.12.01
2025年 12月の診療日時2025.11.22
患者さんの声(15年以上メンテナンスで継続通院)2025.11.20
11.22(土)、25(火)、通常通り診療やります!!2025.11.19
2025年10月の活動記録2025.10.29
2025年 11月の診療日時2025.10.15
2025年9月の活動記録2025.10.10
清明院16周年!!!2025.10.01
2025年 10月の診療日時2025.09.20
2025年8月の活動記録2025.09.01
2025年 9月の診療日時2025.08.15
2025年7月の活動記録2025.08.01
2025年 8月の診療日時2025.07.04
2025年6月の活動記録2025.07.01
2025年 7月の診療日時2025.06.26
2025年5月の活動記録2025.06.01
2025年 6月の診療日時2025.05.10
2025年4月の活動記録2025.05.01
2025年 5月の診療日時2025.04.04
2025年3月の活動記録2025.04.01
2025年 4月の診療日時2025.03.13
2025年2月の活動記録2025.03.01
2025年 3月の診療日時2025.02.06
2025年1月の活動記録2025.02.01
2025年 2月の診療日時2025.01.21
順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10
2024年12月の活動記録2025.01.02
2025年 1月の診療日時2025.01.01
謹賀鍼年!!2024.12.28
年内診療終了!!2024.12.14
2024年11月の活動記録2024.12.01
2024年 12月の診療日時2024.11.07
2024年10月の活動記録2024.11.01
2024年 11月の診療日時2024.10.10
清明院15周年!!!2024.10.09
2024年9月の活動記録2024.10.01
2024年 10月の診療日時2024.09.19
2024年8月の活動記録2024.09.01
2024年 9月の診療日時2024.08.03
2024年7月の活動記録2024.08.01
2024年 8月の診療日時2024.07.10
患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05
2024年6月の活動記録2024.07.01
2024年 7月の診療日時