お電話
03-6300-0763
10:00~21:00(完全予約制)
2019.02.19

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
清明院では女性の患者さんが多い、「股関節痛」。
これは、外側に出るもの、内側に出るもの、動作時に出るもの、動作開始時にのみに出るもの、安静時にも出るもの、大腿部にまで放散するものなどなど、痛みの出方は実に様々。
整形外科で、股関節の変形を指摘されているものも、ないものもある。
この部位の疼痛は、膝関節と同じく、毎日歩行する以上、安静が保てず、症状が遷延しやすい。
また、一時的に疼痛が緩解しても、再発を繰り返しやすい。
鍼灸臨床サイドでは、如何に「人工股関節」という最終手段にさせないか、筋力低下、歩行困難を食い止めるか、がポイントになる。
(もちろん無理、無茶はしません。)
即効性が得られ、なおかついい状態が持続するものの多くは軽症であり、正気の虚が関与しているものであれば、治療に時間がかかることが多い。
しかし、三歩進んで二歩下がるような地味な治療であるが、キチッとやると、キチッとした効果が期待でき、患者さんから非常に感謝される症状でもある。
それくらい、歩行時の腰下肢の疼痛というのは嫌なものだ。
股関節(周辺も含む)に流注する経絡は、ザっと
足陽明胃経(経脈(気衝)、経別(髀関)、経筋(髀枢))
足太陰脾経(経脈(衝門)、経別(髀)、経筋(髀))
足太陽膀胱経(経脈(八髎穴、髀枢、会陽穴)、経筋(会陽))
足少陰腎経(経脈(長強、会陰))
足少陽胆経(経脈(環跳、居髎、気衝)、経別(髀枢)、経筋(髀枢、長強、伏兎))
足厥陰肝経(経脈(衝門、府舍)、経別(前陰部で足少陽と会合))
となり、
(笑・・・足の三陰三陽全部じゃんか!)
奇経では、
任脈(会陰)
督脈(会陰、会陽)
衝脈(会陰、気衝、陰股の内廉)
帯脈(五枢、維道)
陽蹻脉(居髎、環跳、股外の前廉)
陰蹻脉(陰股)
陽維脉(居髎、環跳)
陰維脈(股の内廉、府舍、会陰の傍ら)
となる。
(笑・・・これも全部じゃんか!)
絵が下手だから書かないけど、上記を股関節にズームして図に起こすと、股関節の経絡学的な立体構造が見えてくる。
それを疼痛部位、可動障害の起こっている方向と照らし合わせれば、経絡学をキチッとやっている人であれば、色々な配穴や診どころが浮かぶ筈。
まあ、臨床上多いと感じるのは、脾経胃経、肝経胆経から起こるもの。
それらを勘案して、上手に調整すれば、イケるものはイケる。
つい最近もイケた。
今まさにイケつつある症例もある。
腎の関与がキツイものだと、難しいのかな、という気もする。
【参考文献】
『臓腑経絡学』藤本蓮風他 アルテミシア
『現代語訳 奇経八脈考』李時珍著 勝田正泰訳 東洋学術出版社
『奇経八脈考全釈』李時珍著 小林次郎訳 燎原
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.02.18

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
眠れない患者さん、よくいます。
安定剤、導入剤に頼っているケースが大多数。
暫く使っていると、効かなくなってきたのでと、分量を増やしたり、より強い薬に変えていく。
雪だるま式に増えていく。
・・・そうなる前に、鍼灸をお勧めしたい。
不眠症は、東洋医学では「不寝(ふしん)」と呼んだりする。
明代の大名医、張介賓(張景岳 1563-1640)の『景岳全書』(1624)に曰く。
不寝はただ邪正の二字すなわちこれを尽くすと知るなり。
神が安定すれば眠れる。
神を不安定せしめるものは邪の擾か、営気の不足。・・・
〇
と、単純明快に喝破する。
また、清代の呉鞠通(呉瑭 1736-1820)の『温病条弁』(1798)に曰く。
不寝の原因は甚だ多い。
陰虚で陽納出来ないもの、陽亢で陰に入れないもの、胆熱、肝気(肝用)不足、心気虚、心陰虚、心血虚、蹻脈不和、痰飲擾心。
〇
と、多数のパターンを上げております。
どっちも正しいと思うが、張景岳先生の「所詮は虚実」という斬り方が個人的には好き。
標本主従あるけど、心神の関与はあると診た方がいい。
そして、蹻脈と心神、肝胆と心神に関して、生理と病理を整理するべき。
その上での「所詮は虚実」。
【参考文献】
『症状による中医診断と治療』燎原出版
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.02.10

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話し
参照
◆今回の治療と反省
今回、見事に立春とともに起こった、一連の症状でした。
まず時節柄、内傷としての肝胆の異常は頭に置くべきでしょう。
(決めつけてはイカんけどね)
土曜の食事会での緊張からの緩和、東方医学会での緊張からの緩和、この、「緊張からの緩和」の「緩和」の際に症状が重くなるようなものは、
北辰会では、多くは肝気実型の病変と考えます。
今回は、最初の段階で、それにさらに外邪が絡んでいるものと考えた。
日曜の夜の、発熱時の段階での治療が、あまりにもシャープに決まったため、調子に乗って気を抜いたのがミスでした。
いくら軽くても、風邪気味であった場合、完全に治ってからも1週間、最低でも3日は、重々気を付けて過ごすべきでしたね。
その意味で、水曜日の午後、いやむしろ朝、咽喉がおかしい、声が出にくいと感じた時に、即座に病理を分析して手を打つべきでした。
それを放っておいて、講義で喋り、飲み会で喋り・・・、という流れをもって、迂闊にも「嗄声」という病を完成させてしまいました。(苦笑)
こうなると、邪熱の発生源を「肝の鬱熱」と「中焦の湿熱」と考えて、せっせと治療したものの、「排便や排尿、発汗」というイベントを待って、
一定の期間を経過しないと、もはや即座には声は戻りません。。。orz
・・・いやー、いい勉強になりました。
しかし立春(というか時節の問題)、やはり恐るべし。。。
来年は健やかに立春を迎えたいなあ・・・。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.02.01

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話し
「腹哀」という経穴 ⑤ 参照
◆「肺先」の意味。(竹下の妄想(笑))
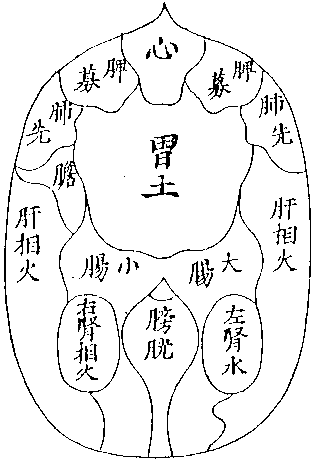
腹哀穴は、日月穴、期門穴(旧説の位置)と縦に並んでおり、鍼灸師とってあまりにも有名な「夢分流腹診図」においては「肺先」と呼ばれる部位の真下あたりに位置する。
『針道秘訣集』には、「肺先」の説明として、
「ここに邪気往するときは息短く喘息、痰出(い)で肩ひじの煩い出る。」
と書いてある。
蓮風先生の『弁釈針道秘訣集』では、
「喘息はむしろ脾募に出る、風寒邪が入ると心下に出る、肝の相火、肺先から心下の邪が結びつくと呼吸困難を起こす。云々・・・」
とある。
蓮風先生らしく、原著に書いてあることをそのまま鵜呑みにするのではなく、必ず実際の現代の自分の臨床と照らし合わせて考えておられることがよく分かるのですが、
まあ、「肺先」というぐらいで、臨床的には呼吸器の病変を反映するんだなと、簡単に理解できます。
ここで当然、じゃあ「先」ってどういう意味??と気になる。
「先」を軽く字解きすると、諸橋徹次の『広漢和辞典』によれば、
①すすむ、すすめる
②さき
③むかし、以前
④死んだ、亡くなった
⑤祖先
⑥さきだち、さきがけ
⑦てびき、紹介
⑧さきぶれ
⑨まず、さきに
⑩さきんずる
⑪先生
⑫碁などで、相手よりも先に碁石を下すこと
⑬姓
と、非常に意味が多いが、個人的には④の「死んだ、亡くなった」という意味が気になる。
白川静『字通』によれば、上記以外の意味では
①死者
②追い越す
という意味があるらしいが、これも個人的には①「死者」が気になる。
夢分流の創始者である夢分斎先生も、首を絞めたり、口鼻を塞いで、呼吸を止めてしまえば、全く健康な人であっても即座に死ぬ、なんていうことは当然知っていたはずだし、
呼吸機能そのものが弱ければ、全身の気血の状態が悪くなり、全ての病気にかかりやすく、治りにくくなる、つまり死に近くなる、ということは当然知っていた筈です。
僕的には、かねてから、この「肺先」というエリアは、その呼吸機能(肺の臓の生理作用)に大きく関わるエリアであり、そこに「先」という文字をあえて入れたのは、単に
「ここは肺の臓の先っぽらへんを示すよん」
という意味”以上の”意味が込められている気がしてならないのです。
「腹哀」という経穴 ③で、小田規矩之介先生の見解として述べたように、腹哀の「哀」の字が「商」に通じ、西方、太陰(経絡で言えば脾肺)を示すということとも繋がって、
夢分斎先生が禅僧であったことも考えると、西方浄土、この世とあの世の境目、順逆を分ける重要な診どころとして「肺先」「腹哀」を意識して診てしまうのです。
ある種の重症疾患や難治性の疾患で、肺先に邪が出ていた場合、治療によってその邪が下外方に移動するか、変わらないか、上内方に移動するか、
沈んでいくかは、けっこう重大な問題なんじゃないかな、な~んて、以前から妄想しています。
・・・とまあ、今日の話は、全くの妄想であり、読者の皆様のご批判を頂ければ幸甚と思います。
割かし、僕の臨床感覚というのは、そういうのが至る所にあります。
もうちょっと続く
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.01.29
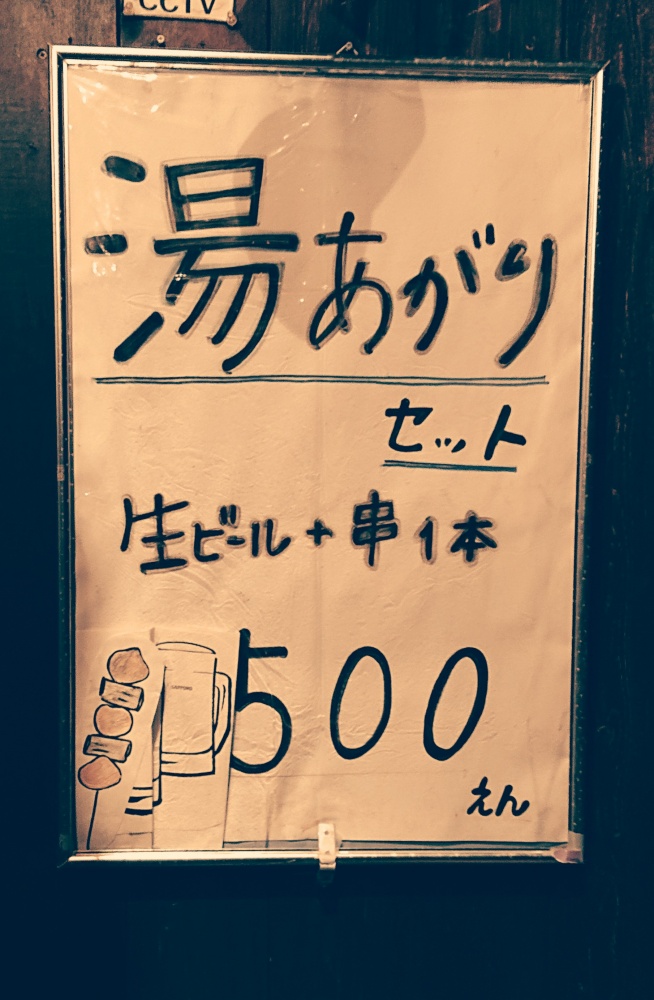
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話し
「腹哀」という経穴 ③ 参照
◆「腹哀」は胆の募穴「日月」、肝の募穴「期門」と近い☆
ここまで、ほとんど誰にも顧みられることの無い、超マイナーな経穴である「腹哀」穴に関して、
1.所属経絡としての魅力、
2.位置的な魅力、
3.横並びの重要経穴群の魅力、
4.字解き(字義解釈)上の魅力
について触れてきました。
これだけ挙げても、まだまだ他にも魅力的なんです、腹哀は。(゚∀゚)
今度は「縦並び」です。
実は腹哀穴のすぐ上には、胆の腑の募穴である日月穴、その上には肝の臓の募穴である期門穴があります。
現行の経穴学の教科書『新版 経絡経穴概論』(日中韓合意WHO採用版)では、期門穴の位置は巨闕穴の外方4寸、第6肋間に取穴する、とあります。
我々が卒業した頃の教科書では、「期門穴」は第9肋軟骨の付着部の下際に取る、と教わっていました。
もともと、期門穴の位置については諸説あり、現在の教科書では「第6肋間説」が採用されているようです。

↑↑この写真でいうと青印は日月穴、その上の赤印が現行教科書の期門穴、下の赤印が旧教科書の期門穴です。
僕としては、鍼灸学生時代に、腹哀穴の真上に日月穴、その真上に期門穴という縦並びの位置関係に着眼していたので、どうも現行教科書の説には馴染めません。
(笑・・・まあ、あそこに反応出ることもあるんだけどね(;’∀’))
腹哀は足太陰脾経上の経穴で奇経八脈の陰維脈と交わり、位置的には帯脈上にも位置し、日月は足少陽胆経上で胆の募穴、期門は足厥陰肝経上で肝の募穴、
この3経の重要穴処が「あそこ」に配されていることに、個人的には深い意味を感じずにはいられません☆
「あそこ」とはもちろん、「膈」付近であります。
続く
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.01.27

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
こないだ、勉強会で、面白いことがあった。
まあ最近はすっかり立春前、という感じがハッキリしてきました。
こんな大都会東京でも、敏感な患者さんの中には、体の変化、風や日差しの変化に気付く人もいるようです。
この時期、足厥陰肝経の終末であり、「三陽五会」とも「百脈が朝会する処」とも言われる「百会」穴が大活躍します。
こないだの勉強会で、
「足が冷えて頭が逆上せる」
という人がいました。
百会穴に鍼をすると、爽やかにのぼせが下がる感覚があって、足が温もる。
また、
「体が火照って熱い」
という人がいました。
百会に鍼をすると、全身が涼やかに冷えて、気持ちがいいという。
同じ経穴に同じように鍼をしても、ある時は温まったり、ある時は冷えたり。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2018.11.13

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
11.11の日曜日は、日本東洋医学会、東京都部会に参加してきました!
(終了後、北辰会関東支部定例会にも参加してきました!!)
今回は、先日このブログで一貫堂医学、森道伯先生に関する記事を書いたときに何度か連絡を取らせていただいた矢数芳英先生が一貫堂医学について語るということで、
お誘いいただき、楽しみにしていました。
この日は朝から女子医大の東洋医学研究所の所長である伊藤隆先生による、藤平健先生に関する講義。
藤平健先生に関しては、以前少し触れました。
丸山昌朗という人物 参照
藤平健先生は、千葉古方、奥田謙蔵先生の流れをくむ、昭和漢方界を支えた重鎮の先生の一人です。
(千葉大の和漢診療科のHPに詳しい紹介ページがあります。)
声が聴き取りやすく、内容も難しくなく、藤平先生の併病理論がよく分かる、非常に聴きやすい講義でした。
2コマ目は日本東洋医学会の元会長である松田邦夫先生による和田東郭先生のお話し。
松田邦夫先生も、一貫堂処方のもとの一つにもなっている、あの『万病回春』を現代語訳されており、今回初めて話を聴けるので楽しみにしていました。
因みに和田東郭先生といえば、今でもよく使われる四逆散、抑肝散の使い手として有名です。
このブログにも何度も登場しています。
「和田東郭」を含む記事 参照
松田先生は盛んに、患者の精神面、医師の精神面など、「心持の大事」を、和田東郭の臨床を通じて説いているように思えました。
蓮風先生もそうですが、やはり大ベテランになると、「心持ち」をこそ重視するようになるのかなあ、と思いましたね。
3コマ目は昭和大学の薬学部の教授である川添和義先生による生薬に関する講義。
大変聴き取りやすい講義で、スライドも見やすく、そういう意味で非常に参考になりました。
(サスガ大学教授、人気の講座を持っているんだろうな、という感じがしました。)
僕は漢方に関しては、必要な患者さんに関しては、「漢方臨床専門数十年」の、ゴリゴリの漢方家の先生を紹介して、一切お任せする主義なので、
細かいことは正直あまり分からないのですが、メーカーによって、同じ名前でも内容物や内容量が違うというのは、使う側からすると大変だろうなあ、
と思いました。
そして最後は矢数芳英先生による「一貫堂医学」に関する講義。
矢数芳英先生は、森道伯先生の弟子で、昭和の日本漢方界の巨人である矢数道明先生の御令孫です。
講義の中で仰っていたように、矢数先生のハングリー精神を感じる、非常に分かりやすい講義でした。
森道伯先生は、結核と脳卒中の治療に苦戦した、それをどうにか予防できないか、ということで発案されたのがいわゆる一貫堂医学である、
また、矢数家が森道伯先生と関わるきっかけとなった、矢数格先生がマラリアの治療を受けた五積散の使い方や、芳英先生自身の奥様の荊芥連翹湯の症例など、
聴きどころがたくさんあり、あっという間に時間が経ちました。
また今回は、来年の日本東洋医学会の会頭でもある花輪壽彦先生とも、少しお話が出来ました。
今後、東京都内でも、清明院のように東洋医学をやっている数少ない鍼灸院と、漢方家の先生方で手を組んで、患者さんの益になる治療がドンドン出来たらいいですね。
医師と鍼灸師の間にある、見えない壁のようなものは、こちらから積極的に取り払っていこうと思います。
そして終了後は北辰会へ。
今回の飲み会では、S先生がいつも以上に冴え渡っていました☆(^^)
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2018.10.29

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話し
参照
◆命名の由来の続き~生薬としての効能に関して
前回、もともとの名前である「ローズマリー」、また、和名である「マンネンロウ」について紹介しました。
今日は中国名の「迷迭香(めいてつこう)」について、考えてみたいと思います。
これの命名の由来は正直分かりませんでしたが、「迷」はもちろん「迷う」、「迭」は「代わる、滑る、入れ替わる」、「香」はそのままの意味でしょうから、
「迷うようにあっちこっちに代わるがわる生える、香気の強い木」
ってな感じじゃないでしょうか。
(笑・・・まったく間違ってたりして。(゚∀゚) もし詳しい方おられましたらご教示下さいませ<m(__)m>)
一応、生薬としての効能は「健胃、鎮痛、駆風」と出てきました。
また、性味は「辛・温」、帰経は「心・肝・脾・肺」とも出てきました。
(温帯で採れるからといって、冷やすわけではないのね。。。本によっては清熱解毒と書いてあることもあるんだが。。。)
横浜薬科大学編『漢方薬膳学』によれば、「発汗解表、健胃、鎮静」などと出てきます。
また、ハーブに詳しい先輩の話では
「働きはハッキリしていて瀉法的」
「香りが強く心肺に作用しやすい、香水としても使われる(料理でも)」
「経験的にはハーブの中でも比較的強く、発散、開竅、通気、清気という印象」
といった情報が得られました。
総合すると、どうも気血を巡らせる働きが強く、瀉法的に働く薬効がある、ということが分かりますね。
心肺に作用しやすいということから、呪術的、宗教的側面を持ちやすいことも頷けます。
続く
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2018.09.22

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
そろそろ二十四節気では「秋分」ですね。
いよいよ、本格的に秋になります。
東京も、21日の雨の日に明らかにガクッと気温が下がりました。
その3日4日前あたりから、それまでになかったような症状が出る患者さんがチラホラいます。
今多いのは咳、ノド痛、たまに便秘や下痢などの消化器症状ですね。
肺の臓、脾の臓との関りがあることがほとんどです。
北辰会方式では、心の臓や肝の臓を非常に重視しますが、何でもかんでもそれでやるわけではないです。
三因制宜を考えて、時宜を得た治療を行います。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2018.09.15

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
さて、マニアックな話、ドンドンいきましょう。
ドンドン読者を置いていきます。
そしてみんな離れていって、終いには一人になりそうです。(爆)
・・・ともかくここまで、一貫堂医学における「三大体質・五大処方」について書いてきました。
よく勘違いされがちなこととして、
「一貫堂って、全ての患者を3つの体質に分類するんでしょ?それも全部実熱でしょ??そんなん、無理あるっしょ~~!!(;’∀’)」
というミスリード。
普通に考えて、そこだけ切り取って、名医・森道伯を語れる訳ないですね。(・ω・)ノ
矢数道斎(格)先生のまとめた『漢方一貫堂医学』には、森道伯先生のほぼ晩年の3年間のカルテに使った方剤が集積して一覧表にしてありますが、
当然ながら「それ以前の」数十年がある訳です。(笑)
まあ、色々な症例やエピソードがあると思うんですが、有名なのは「スペインかぜVS森道伯」のエピソードでしょう。
まず「スペインかぜ」を簡単に説明しますと、1918年~1919年(大正7年~8年)にかけて起こった、アメリカ発の強毒性インフルエンザのパンデミック(世界的大流行)です。
アメリカ発なのにスペインかぜと呼ぶのは、情報源がスペインだったから、だそうです。
ちょうどこの時は第一次世界大戦(1914~1918)の末期であり、このスペインかぜが大戦を早期に集結させた要因の一つである、という見方もあるぐらいの大事件であったようです。
そのくらい被害は大きく、全世界で5億人が感染、死者は5千万人~1億人、とも言われています。
日本にも被害が広がり、現在タレント論客として活躍している竹田恒泰さんの曾祖父君にあたる竹田宮恒久王をはじめ、多くの日本人が感染しました。
この時、森道伯先生はスペインかぜを3つに分類し、
胃腸型・・・香蘇散+茯苓・白朮・半夏
肺炎型・・・小青竜湯+杏仁・石膏
脳症型・・・升麻葛根湯+白朮・川芎・細辛
で治療し、たいへん効果を挙げたそうです。
これらも、現在でもよく使われる、割かしなんてことない処方なんですが、この処方からしても、決して実熱のみを重視していたなんて思えません。
スペインかぜの弁証論治を、非常にシンプルな形に落とし込んだように見えます。
因みに各方剤の出典は、
香蘇散は北宋の国定処方集である『和剤局方』、
小青竜湯は後漢の張仲景(150?-219)による『傷寒論』、
升麻葛根湯は『閻氏小児方論』という本が出典で、有名な葛根湯の変方かと思いきや、やや似て非なる配合の薬です。(笑)
僕のPCに入れてある『東洋医学辞書』では
葛根湯は葛根5.0・麻黄・大棗各4.0・桂枝・芍薬・生姜各3.0・甘草2.0
升麻葛根湯は葛根5.0・芍薬3.0・升麻・乾生姜各2.0・甘草1.5
と出てきますが、『中医臨床のための方剤学』では
葛根湯は葛根12g・麻黄、生姜9g・桂枝、炙甘草、白芍、大棗6g
升麻葛根湯は赤芍6g・升麻、葛根、炙甘草3g
と、ずいぶん違います。
こういうの(同じ方剤名でも時代や文献で構成生薬が違う)も、方剤学のややこしいところですね。(苦笑)
まあともかく、
香蘇散は風寒表証+気滞の薬で、現代ではストレスからくる肩凝りだの胃もたれだのといった、肝鬱や肝胃気滞によく使われる薬です。
小青竜湯は風寒表証+脇下の水飲の薬で、現代では「くしゃみ三回小青竜」な~んていう、実に胡散臭い謳い文句があって、花粉症によく使われる薬なんですが、
何も考えずに長期服用すれば徐々に内熱が籠っていき、別の病を形成します。(~_~;)
西洋薬と比べて、副作用がなくて眠くならないから助かるわ、な~んつって、冬から春に長期服用している患者さん、ホントに多いです。
升麻葛根湯は、小児の麻疹(はしか)の薬として有名で、肺胃の熱毒を叩く薬です。
これらを強毒性のインフルエンザに巧みに応用した訳ですね。
・・・まあいずれにせよ、よく後世派と言われる一貫堂ですが、古方派の使うような方剤も臨機応変に臨床応用していたことが分かります。
(そういえば後世派、古方派についても書いてなかったですね。いい機会なんでこれが終わったら書きましょう。)
次回、感染症に対する東洋医学の考え方を書きます。
続く
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.07.08
2016.05.09
2016.04.12
2016.04.28
2015.06.04
2012.12.23
2014.02.17
2014.04.26
2025.04.01
2025年 4月の診療日時2025.03.13
2025年2月の活動記録2025.03.01
2025年 3月の診療日時2025.02.06
2025年1月の活動記録2025.02.01
2025年 2月の診療日時2025.01.21
順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10
2024年12月の活動記録2025.01.02
2025年 1月の診療日時2025.01.01
謹賀鍼年!!2024.12.28
年内診療終了!!2024.12.14
2024年11月の活動記録2024.12.01
2024年 12月の診療日時2024.11.07
2024年10月の活動記録2024.11.01
2024年 11月の診療日時2024.10.10
清明院15周年!!!2024.10.09
2024年9月の活動記録2024.10.01
2024年 10月の診療日時2024.09.19
2024年8月の活動記録2024.09.01
2024年 9月の診療日時2024.08.03
2024年7月の活動記録2024.08.01
2024年 8月の診療日時2024.07.10
患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05
2024年6月の活動記録2024.07.01
2024年 7月の診療日時2024.06.05
2024年5月の活動記録2024.06.01
2024年 6月の診療日時2024.05.10
2024年4月の活動記録2024.05.01
2024年 5月の診療日時2024.04.13
(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02
2024年3月の活動記録2024.04.01
2024年 4月の診療日時2024.03.14
2024年2月の活動記録2024.03.01
2024年 3月の診療日時2024.02.15
2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04
3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03
3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02
2024年1月の活動記録2024.02.01
2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01
2024年 2月の診療日時2024.01.11
2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05
診療再開!!2024.01.01
2024年 1月の診療日時2023.12.30
2023年、鍼療納め!!2023.12.21
(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01
2023年 12月の診療日時2023.11.26
患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25
患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22
12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21
今週からの講演スケジュール2023.11.16
日本東方医学会学術大会、申し込み締め切り迫る!!