お電話
03-6300-0763
10:00~21:00(完全予約制)
2012.08.09

**********************************************************************************************
![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
乳製品は体にいい?
乳製品は体にいい?(その2)
乳製品は体にいい?(その3)
乳製品は体にいい?(その4)
乳製品は体にいい?(その5)
乳製品は体にいい?(その6)
では、どんどんいきます!
前回、「コーヒー」について書きました。
毎日毎日、患者さんの話を聞いていると、コーヒーや紅茶、緑茶などといった、いわゆる「カフェイン類」を過飲している人は多く、キチッと養生指導しなくてはいけないことが多いです。
これまでに多い人で、1日10杯も飲んでる、なんて人もいました。
ナンボいい鍼をしても、患者さんが誤った食生活を続けていたりすると、治療の大きな妨げになるものです。
カフェイン含有食品として有名なのは、紅茶、緑茶、コーヒーあたりです。
(因みに含有量的には紅茶>お茶>コーヒーの順ですが、インスタントコーヒーはレギュラーコーヒーの約70倍ものカフェイン量なんだそうです。。。(゜o゜))
問題はカフェインが入ってるものを、その人の”適正量”、”許容量”を超えて摂ってしまっているかどうか、また、それがどの程度、今回の症状に影響を与えているかどうか、です。
カフェインについて栄養学的に詳しく、一般人に分かりやすく解説したサイトは山ほどありますので、ここではしませんが、”いい作用”としては、
脳の働きを活発にするとか、利尿作用、虫歯予防作用、胃液分泌促進あたりが有名です。
反対に、過飲した場合の”悪い作用”は、胃潰瘍や卵巣嚢腫や乳腺嚢腫になりやすいとか、イライラや頭痛といった中毒症状が出るとか、です。
このカフェイン類というのは、東洋医学的にはどういう意味を持つのでしょうか。
・・・これは摂った人の、その時の状態によって、発現する作用が違ってくると思いますので、これまた臨機応変に、個別に考える必要があると思いますが、基本的には肝気を鼓舞する、という押さえ方で良いと思います。
因みに、何度も言うようですが、そもそも「過飲」の量だって、人それぞれ違います。
興味深いことに、患者さんに聞いていると、カフェイン類を摂ると、シャキッとする人と、ホッとする人の2パターンがおります。
同じ人でも、状況によって違う(逆の反応を示す)場合もあります。
会社にいる時はシャキッとするけど、家にいる時はホッとする、とかね。
家でカフェインを摂るとホッとする人には、寝る前にカフェイン類を摂った方が、かえってよく眠れる、どうして??なんておっしゃる方もいます。
このことから、興奮状態になったり、安静状態になったりすること(精神情緒の変動)にカフェインが関わる、と考えられ、それならば、東洋医学的には、
気の巡りや精神状態や思考機能に大きく関わる訳ですから、臓腑で言えば「肝の臓」や「心の臓」「脾の臓」あたりに作用する面が相対的に大きいのかもしれません。
つまり、「肝の臓」や「心の臓」、「脾の臓」を中心に病んでいる人は、摂取量に注意が必要、と考えます。
「肝」って何ですか?(その13)
「脾」って何ですか?(その9)
「心」って何ですか?(その7) 参照
このように、臨床的にはあくまでも総合的に判断するべきで、ある情報のみをもって何かを断言することはできません。
・・・とまあ、このシリーズに関して、こんなもんなんですけど、山の子供さんからご質問いただいたので、せっかくなんで、タバコの問題もついでにいっときましょうかネ。
やはり皆さん、この辺の話は興味あるんだな。。。
◆参考文献
『食材効能大辞典』東洋学術出版
『東方栄養新書』メディカルユーコン
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.07.22
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
前回のお話・・・
では続きいきます!!
東洋医学では膝が痛いからって、必ず膝に原因がある、とは考えません。
単純に歩きすぎたとか、急激に太ったとかで、膝自体に物理的な負荷がかかりすぎた場合で、膝周囲のみ治療すればよくなる、というケースもないわけではないですが、
それは問題が膝のみにある、ごく軽いものであって、実際はそれ以外にも、五臓六腑の異常が関係している場合、外から全身が冷やされた場合など、
様々な病因があり、それを明らかにして、それに合わせて、治療します。
まあそうしないと、鍼灸院にわざわざ来るような大概のものは、なかなかよくなりません。
現在の日本の医療体制では、我々鍼灸院にみえる膝痛の患者さんは、まず最初に整形外科に行って治らず、次に整体や整骨院に行っても治らず、
悪く言えば、いろんな医療にさんざんいじくり回されたあとの、膝痛の患者さんが多いのです。(苦笑)
ですので、簡単で単純なものは、鍼灸院にたどり着く前にほぼ治ってしまっているので、我々のところに来るようなものは、五臓六腑の慢性的で複雑な変調の関わる、
ある意味重傷な膝痛が多いと思います。
ここで我々の臨床上多いのが、「肝の臓」、「脾の臓」の異常です。
「肝」って何ですか?(その13)
「脾」って何ですか?(その9) 参照
まあ、詳しい話をしていくと長くなりすぎるし難しくなっていっちゃうのでしませんが、この2臓を整えることで、よくなる膝痛は非常に多いです。
だから、患者さんとしては意味不明だろうけど、膝痛の治療なのに腕に一本、とか、頭に一本、という場合がよくあります。
最近診た膝痛の患者さんは、みんな上半身への刺鍼でよくなっております。
西洋医学の処置で治らなかったものが、です。
現代の「普通の」医学で治らないものを治す、こういうのも、東洋医学の存在意義だと思います。
((笑)・・・どうして水が溜まるかの細かい話、書こうと思ったけど、時間がなかった、あしからず・・・。)
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.07.10

**********************************************************************************************
![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
続きいきます!!
◆「肝の臓」と「疲労」と「疲労感」の続きの続き
前回、労働の程度がそれほど重くなく、体を診てもそれほど疲労がたまっている風でもないのに、強い疲労感を自覚するケースがあることと、
そのメカニズムとして、肝の臓が大きく関わることが多い、というお話をしました。
で、今日は、その逆パターンのお話。
労働の程度からしても、実際に診た、体の状態からしても、体は明らかに疲労しているにも関わらず、患者さんに聞いても、まったく自覚がない、という場合があります。
そういう患者さんにもし、
「これ、相当疲れてるよ。」
と声をかけたとしても、
「え?そうですか??全然そんな風に感じないんだけど・・・。」
となるだけです。(苦笑)
・・・なぜ、こういうことが起こるのか。
これは、体に実際に起こっていることを「正確に認知する」システムの異常であることが少なくないです。
ですから、こういう患者さんを正しく治療していくと、「疲労感」を正しく認識するようになり、大病を未然に防ぐことが出来ます。
よく、患者さんから、
「鍼を受けるようになって、以前の自分はすごく無理をしていたと分かりました。」
なんて言われることがあります。
こうなると、我々としては
「しめしめ・・・。良く効いとるワイ。」
なワケです。
東洋医学的な、「感覚認知のシステム」を理解する上で重要な臓腑といえば、「肺の臓」と「心の臓」でした。
この二臓のうち、「認知機能」において特に重要なのが「心の臓」であり、この「心の臓」の働きがしっかりとなされるために重要なのが、「肝の臓」なのであります。
そのことについても以前、「心肝同源(しんかんどうげん)」という言葉を使って、ご説明いたしました。
また「肝の臓」は、「肺の臓」とも深く関わり、人間のあらゆる感覚というのは心、肝、肺の三臓が主に強調しあって、正常な状態が保たれている、と考えられています。
肝と肺の関わりについては 「肺」って何ですか?(その3) 参照
この三臓の働きが何らかの原因によって不和を起こしていたりすると、感覚の異常が起こり、痛いはずのものが痛くない、とか、大して痛くないはずのものが猛烈に痛い、
とか、疲れているはずなのに、それを自覚できない、とか、疲れてないはずなのに強い疲労感を感じる、とかいう、ややこしいことが起こってきます。
そしてこれが、臨床上は非常に多いと思うし、あらゆる大きな病の原因になっていくと思います。
で、それには「肝の臓」の調整が、非常に重要である、と。
次回、そんな超重要な「肝の臓」の、養生法のお話をちょっとして、終わろうかな、と思います。
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.07.07

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
「肝(かん)」って何ですか?(その1)
「肝」って何ですか?(その2)
「肝」って何ですか?(その3)
「肝」って何ですか?(その4)
「肝」って何ですか?(その5)
「肝」って何ですか?(その6)
「肝」って何ですか?(その7)
「肝」って何ですか?(その8)
「肝」って何ですか?(その9)
「肝」って何ですか?(その10)
「肝」って何ですか?(その11)
続きいきます!
◆「肝の臓」と「疲労」と「疲労感」の続き
前回、実際の症例から、「実際の肉体疲労の程度」と「患者さんの自覚的な疲労感」に、大きくギャップがある場合がある、というお話をしました。
また、肝の臓が古典の中で「罷極の本(ひきょくのほん)」な~んて呼ばれ、疲労回復に重要な働きを持つことについても触れました。
そもそもこの「疲労」というものについては、西洋医学的にも、なかなか定義があいまいなシロモノのようなんですが、疲労を東洋医学的に、
「気血の消耗と、気血の停滞」
と定義した場合、その感じ方に個人差が出るのはどういうことでしょう。
まず、疲労の「程度」を決定づけるのは、気血の消耗と停滞の「程度」なワケですから、基本的には作業が長時間で、重労働であればあるほど、疲労の程度は増すハズです。
でも、同じ労働をしたって、人によって感じる疲労感は同じではありません。
まあ、スポーツマンと一般人では体力が違う、というのは当たり前ですが、年齢も性別も同じ、基礎体力もほぼ同じ人が、同じような労働をしても、
自覚する疲労感には必ず違いが出ます。
コレは、ひとつにはその人の「肝の臓」が、どれだけ疲労回復力(疏泄力)を持っているかによって変わって来るんだと思っています。
人間、一人一人顔も声も違うように、五臓六腑の堅脆も違うのです。
つまり、
大したことない疲労でも、もともと肝の臓が弱い人にとっては、回復が遅いため、疲労感を強く感じやすい
という訳です。
肝の臓が病んでいると、疲労がなかなか回復できないのです。
そして、そこにさらに疲労がたまると、弱っている肝の臓にさらに負担をかけることになり、さらに弱る、という悪循環に入っていきます。
コレが、様々な大病のもとになる、重要な東洋医学的メカニズムの一つだと思います。
〇
では逆に、カラダは明らかにかなり疲労しているのに、それを「大したことない」と認識する、あるいはまったく感じないという場合は、
どう考えたらいいんでしょう。
次回に続く。
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.07.05

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
「肝(かん)」って何ですか?(その1)
「肝」って何ですか?(その2)
「肝」って何ですか?(その3)
「肝」って何ですか?(その4)
「肝」って何ですか?(その5)
「肝」って何ですか?(その6)
「肝」って何ですか?(その7)
「肝」って何ですか?(その8)
「肝」って何ですか?(その9)
「肝」って何ですか?(その10)
久々に「肝の臓」について、ちょっと書き足しておきます。
というのも、最近診た患者さんで、「肝」について改めて考えさせられ、そのことについて、
「この”「肝」って何ですか”シリーズに書いといたっけな・・・??」
と思ったので、久々にザーッと読み返してみると、書いていませんでした!(゜o゜)
・・・という訳で、久々に書き足します。
(笑・・・こういうことがすぐにパッと出来るのも、ブログの良さだね。)
◆「肝の臓」と「疲労」と「疲労感」
こないだ、こんな患者さんがみえました。
「カラダが重だるい、しんどい、もう年だから、もう年だから・・・。」
とおっしゃる男性。
・・・といっても、その方はまだ40代前半。
どう考えても年齢的には”言うほど”年ではないです。
見た目だってそんなに老けこんでいる様子もない。
でも、彼曰く、
「ストレスなんて関係ない。まったく関係ない。だって常にあるから。精神的には全く問題ない。ただ、年だから・・・。」
とおっしゃる。
この時点で分かるのは、
1.精神的なストレスに常にさらされている自覚はあるが、それと体の症状との因果関係を認めたくない。
2.疲労感、倦怠感を強く自覚しており、それを自身の年齢のせいだと思いこんでいる。
という2点です。
そりゃあ確かに、20代の頃と比べたら、体力的には落ちてて当たり前です。
でもそれを、どうとらえるかで、カラダに感じる感覚、自覚症状は全然違ってきます。
『黄帝内経(こうていだいけい)』の中の有名な言葉で、「肝は罷極(ひきょく)の本」という言葉があります。
(『黄帝内経素問』六節蔵象論(9))
この聞き慣れない”罷極”という言葉の意味については、最近、蓮風先生のブログにも出てきました。
要は、「罷極」とは「筋肉の疲労」のことであり、それと最も関係が深いのが「肝の臓」だよ、ということです。
ここでいう「疲労する」ということの定義は、何らかの作業により気血を消耗し、気血の停滞を生むことです。
その消耗や停滞を取り去り、疲労を回復させてくれるのが「肝の臓」の”疏泄(そせつ)作用”という働きであることは、すでに説明しました。
ここでさらに、実際の疲労の程度そのものと、自覚的な疲労”感”との関わりを考えた場合、ここにアンバランスが生じるのも、重要な病理であり、
これもやはり「肝の臓」と深く関わります。
つまり、肉体的には大して無理をしてないから、気血の消耗の程度や停滞の程度も軽いにも拘わらず、強い疲労感を覚えるのは、カラダに実際に起こっていることを「認知する」システムの異常か、
あるいは患者さん自身の表現力の無さや、あるいは単なる大げさか、ということを考えねばなりません。
長くなってきたので、次回に続く・・・。
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.05.05

**********************************************************************************************
![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
「血(けつ)」って何ですか?
「血」って何ですか?(その2)
「血」って何ですか?(その3)
続きいきます!
◆血が不足すると問題発生
これまでの話で、東洋医学における「血」というものは、基本的には「飲食物」が主な原料となり、足らなくなると「腎精」が「血」に変化してくれることによって不足がフォローされ、
主として「血脈」の中を流れて、全身を隅々まで循環し、必要に応じてカラダを栄養するもの、でした。
また、睡眠時など、あまり使われない時は「肝の臓」に蓄えられている、というお話もしました。
そして、「血」が循環する際の原動力や律動性には「心の臓」や「肺の臓」が、飲食物を消化吸収するためには「脾の臓」や「胃の腑」が、
「腎精」から「血」に変化するには「腎の臓」の働きが大きく関わり、「血」の生成、作用は、実に様々な臓腑の働きに支えられているよ、
というお話でした。
・・・で、今日は、”「血」が不足する”とはどういうことか、を考えてみたいと思います。
上記のようなメカニズムで生成される訳ですから、当然、「脾の臓」や「胃の腑」に異常があって、飲食物をうまく消化吸収出来なければ、
「血」が生成されにくくなり、不足が起こってきます。
それでも、「腎の臓」がしっかりしていて、「腎精」をガッチリ蓄えてくれていれば、不足をフォローできます。
また、「肝の臓」に「血」がたっぷりと貯蔵されていれば、ここからも不足をフォローすることが出来ます。
ですので、”脾胃が弱い=必ず血が不足する”という短絡的な考え方はNGなのです。
しかし、脾の臓や胃の腑が弱く、飲食物から「血のもと」を取り込めない、しかも腎の臓も弱っていて、「腎精」による血のフォローが出来ない、
なおかつ肝の臓にもあまり貯蔵出来ていない、ということになると、これは”全身的な血の不足”が起こります。
まずコレが一つ重要。
こうなると、カラダを潤すことが出来なくなるワケですから、いたるところがパサパサになってきます。
具体的には皮膚、髪、爪がパサパサ、弱く脆くなり、全身的に血色が悪くなり、唇や舌の色も褪せて白くなってきます。
(コワイネ~)
もう一つのパターンとして、「血」の全体量としてはあるんだけど、巡る力が弱い、あるいは何かによって邪魔されてるために、停滞してしまって、
必要な部分に届かず、”部分的に”足らなくなるパターンです。
皮膚に足らなければ痒みを起こしたり、目に足らなければ眼精疲労を、筋肉に足らなければこむら返りやけいれんなどなど、実に様々な症状を引き起こします。
これが、”部分的な血の不足”です。
二つ目にはコレが重要です。
・・・ちなみにこの、「部分的な血の不足」の原因の一つである、”停滞してしまって、使い物にならん血”のことを東洋医学では「瘀血(おけつ)」と呼んでおります。
「瘀血」については、素人の方でも、聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。
以前、このブログでも紹介しました。
要はこの瘀血が、正常な血の運行を物理的に邪魔して、必要な部分に届かないと、様々な症状が起こす場合があるのです。
それ以外にも、肝や心や肺の異常により、「気の停滞」が起こると、血の正常な循環が保てなくなる、というケースもあります。
・・・このように、「血の不足」と一口に行っても、東洋医学的にはまずそれが「全身的なのか、部分的なのか」を考え、それらのメカニズムまで考え、対処、治療しております。
ちなみにちなみに、言うまでもないですが、東洋医学の言う「血の不足(血虚)」と、西洋医学の言う「貧血」とは別物ですので、あしからず。(苦笑)
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.05.03

**********************************************************************************************
![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
「血(けつ)」って何ですか?
「血」って何ですか?(その2)
続きいきます!
◆「血」の居場所
最初に述べたように、「血」は「血脈」をその通路として全身を巡回し、全身の各部位を栄養します。
ドックンドックンと、律動的に、全身を巡っております。
ドックンドックンと押しこくられるパワーは「心の臓」が関与し(主血作用)、その律動性は「肺の臓」が、主に関与(治節を主る)しています。
「血」の通路であるこの「血脈」は、「心の臓」と関係が深いです。
・・・というよりも、「心の臓」自体が、ある意味「血脈」の一部、とも考えられます。
胎児が育っていく過程で、「血脈」のある部分が膨らんで、特別な働きを持ったモノ、これが「心の臓」であるとも考えることが出来ます。
〇
話がそれたので戻しますが、「血」というのは、例えば運動して筋肉を使えば筋肉に、パソコン作業で目を使えば目に、すぐにサッと集まって、その部分の働きを支えてくれます。
(まあ、燃料みたいなもんですナ。無尽蔵ではないけど。)
人間が、ある部分を使う時は、その部分には「気と血」が必要なのです。
だからやり過ぎ(使い過ぎ)たら休ませて、その間に「気血」を生成して、また使う、これの繰り返し以外あり得ないのです。
これは自然の摂理です。
また、あまり体を使っていない時、つまり寝ている時なんかは、「血」はどこにいるかというと、全身を巡ってないわけではないですが、
日中ほどは必要とされないので、主に「肝の臓」に貯蔵されています。
このように、東洋医学の言う「血」というものは、肝、心、脾、胃、肺、腎など、五臓六腑と密接に関わりながら、「気」や「精」というものとも深く関わりつつ、
全身を栄養し、潤してくれているのです。
だからこの「血」が不足すると、体が栄養不足を起こし、パサパサになります。(苦笑)
次回はその具体例のお話。
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.04.17
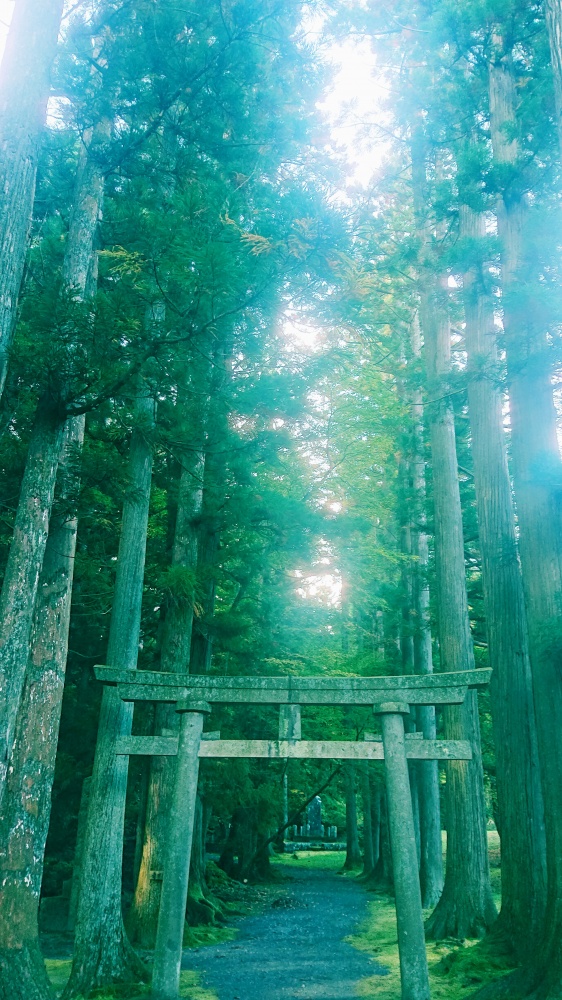
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
続きいきます!!
◆経絡は絶えず循環している
前回までで、「経絡」のメインルートは12本あり、それを「正経十二経」と呼び、一本一本が関係の深い臓腑をもっており、
それは全身を複雑なルートで、絶えず循環している、というお話をしました。
では、どのような順番なのかというと。
肺経→大腸経→胃経→脾経→心経→小腸経→膀胱経→腎経→心包経→三焦経→胆経→肝経
という順番で、全身を循環していると考えられています。
・・・な~んて言われても、ワケ分かりませんわな。(笑)
まあ、ここはあんまり、専門的にならないように、深入りしないように解説しますが、経絡というのは、それぞれが関連する臓腑をもつことと、
もう一つ重要なのが、「手を中心に流れる」ものと、「足を中心に流れる」ものに分けられることです。
例えば、「肺経」であれば肺の臓と深く関わりながら手に流れ、「肝経」であれば肝の臓と深く関わりながら足に流れる、という具合です。
そう考えると、
肺経(手)→大腸経(手)→胃経(足)→脾経(足)→心経(手)→小腸経(手)→膀胱経(足)→腎経(足)→心包経(手)→三焦経(手)→胆経(足)→肝経(足)
という順番になるのですが、これを見ると、経絡の気は手→手→足→足→手→手・・という風に、手から足へと巡り、再び手へと、順番に巡っていることが分かります。
こうやって経絡は、手足、すなわち上下の気の流れのバランスをとってくれているのです。
また、体内の臓腑(深部)にも、皮膚表面(浅部)にも巡ることで、体の深部の気と、浅部の気とのバランスもとっており、上下、左右、前後、内外の気血のバランスの恒常性は、
この「経絡」の循環システムが正常に機能して、はじめて成り立つものと考えているのです。
次回は、経絡それぞれが持つ特長について、ちょっと触れときます。
「経絡」って何ですか?(その5) に続く
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.04.16

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
続きいきます!!
よく、巷の治療院の壁に掛けてあるこんな図・・・。↓↓

(↑↑清明院の院内にもかけてあります。これは某先生から開業祝いに頂いた大切な額です。)
これが、人体の「経絡経穴(けいらくけいけつ)」を図示したものです。
東洋医学では、経絡が人体の「気の主要な通り道」であり、経絡上に「経穴」というものが存在している、と考えます。
これは、機械で計測することも出来ませんし、目で見ることも出来ません。
(一部計測出来るという主張もありますが、それはあくまでも”一部”に過ぎません。)
術者や患者さんが、”感じ取る”、”実感する”ことでしか、その存在を確認することが出来ない代物です。
だからよく、画像や数値で証明できない概念を基本に置いているということで、
「東洋医学は怪しい、胡散臭い。」
なんて言われてしまうことがあるんですが、東洋医学を実践する立場としては、まずコレの存在を肯定せずして、話は始まらないところがあります。(笑)
ですので、我々の医学を分かっていただく上で、ここはとても大事なことですから、これに関するお話をしております。
前回、経絡の主要なルートは12本ある、というお話をしました。
その12本それぞれは、一本一本に、関わりの深い臓腑があります。
東洋医学では、人体には6つの臓と、6つの腑があり、主要な12個の臓腑がある、と考えております。
この六臓六腑一つ一つが、協調し、それぞれの機能を補い合い、恒常性を保っている、と考えます。
これらの12臓腑一つに一本、それぞれ経絡が存在します。
なので合計12本存在するワケです。
これを、例えば肺の臓に属する経絡のことを、肺の経絡だから「肺経(はいけい)」と呼び、肝の臓に関する経絡なら「肝経(かんけい)」といいます。
(笑・・・そのまんまです。簡単です。)
で、これらは一定の規律に従って、順番通りに「循環」しております。
(まあそのように考えられております。)
「経絡」って何ですか?(その4) に続く
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.04.14

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
昨日からあいにくの雨が続いておりますが、春は本来、さわやかな季節です。
二十四節気も、「清明」に入って、早1週間がたちました。
もう、さすがにダウンやコートの時期ではないようです。
(苦笑・・・こないだダウン着て出たら暑かった~)
この冬お世話になった強力なアウターたちを、一気にクリーニングに出してしまおうと思います。
東洋医学の聖典『黄帝内経(こうていだいけい)』にも、
「・・・春は”生じる”季節・・・」
とあります。
(『素問 陰陽離合論(6)』など)
草木が芽吹き、新緑が生き生きとして、風が吹き、自然の勢いを感じる時期です。
しかし、せっかくの美しい春も、花粉症やアレルギー体質の人にとっては、必ずしもいい時期ではないようです。
以前述べたように、アレルギー症状というのは、現代医学的には「人体の免疫機能のイタズラ」なんて言われますが、このいわゆる「免疫」の働きと、
東洋医学の言う「肝の臓」の働きは、だいぶクロスオーバーする部分があります。
春のカラダ 参照
たまに、患者さんによっては、
「小さい頃から春は具合が悪く、今でも春が近づくたびに憂鬱で・・・。」
なんていう声を聞くこともありますが、実は春の養生法としては、これが余計よくないのです。
痛い痛いと思っていると本当に痛くなる、なんてことがあるように、イヤだイヤだと、対象をマイナス感情ばっかりでとらえていると、
本当に気の停滞を起こして、実際に「肝の臓」の働きを余計低下させ、症状が重くなってしまう面があるのです。
結果的に余計に春が嫌いになる、症状も改善しない、という悪循環です。
これを断ち切るために、平素から(理想的には冬からの)の正しい鍼治療と、体調管理、発想の転換が重要なのです。
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.07.08
2016.05.09
2016.04.12
2016.04.28
2015.06.04
2012.12.23
2014.02.17
2014.04.26
2025.12.12
患者さんの声(睡眠障害、その他不定愁訴)2025.12.05
2025年11月の活動記録2025.12.01
2025年 12月の診療日時2025.11.22
患者さんの声(15年以上メンテナンスで継続通院)2025.11.20
11.22(土)、25(火)、通常通り診療やります!!2025.11.19
2025年10月の活動記録2025.10.29
2025年 11月の診療日時2025.10.15
2025年9月の活動記録2025.10.10
清明院16周年!!!2025.10.01
2025年 10月の診療日時2025.09.20
2025年8月の活動記録2025.09.01
2025年 9月の診療日時2025.08.15
2025年7月の活動記録2025.08.01
2025年 8月の診療日時2025.07.04
2025年6月の活動記録2025.07.01
2025年 7月の診療日時2025.06.26
2025年5月の活動記録2025.06.01
2025年 6月の診療日時2025.05.10
2025年4月の活動記録2025.05.01
2025年 5月の診療日時2025.04.04
2025年3月の活動記録2025.04.01
2025年 4月の診療日時2025.03.13
2025年2月の活動記録2025.03.01
2025年 3月の診療日時2025.02.06
2025年1月の活動記録2025.02.01
2025年 2月の診療日時2025.01.21
順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10
2024年12月の活動記録2025.01.02
2025年 1月の診療日時2025.01.01
謹賀鍼年!!2024.12.28
年内診療終了!!2024.12.14
2024年11月の活動記録2024.12.01
2024年 12月の診療日時2024.11.07
2024年10月の活動記録2024.11.01
2024年 11月の診療日時2024.10.10
清明院15周年!!!2024.10.09
2024年9月の活動記録2024.10.01
2024年 10月の診療日時2024.09.19
2024年8月の活動記録2024.09.01
2024年 9月の診療日時2024.08.03
2024年7月の活動記録2024.08.01
2024年 8月の診療日時2024.07.10
患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05
2024年6月の活動記録2024.07.01
2024年 7月の診療日時2024.06.05
2024年5月の活動記録2024.06.01
2024年 6月の診療日時2024.05.10
2024年4月の活動記録2024.05.01
2024年 5月の診療日時2024.04.13
(一社)北辰会、組織再編。