お電話
03-6300-0763
10:00~21:00(完全予約制)
2019.04.09

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
最近のお話し
参照
前回書いたように、葛根湯は、桂枝加葛根湯に麻黄を加えたもの。
で、桂枝加葛根湯は、桂枝湯に葛根を加えたもの。
今日は
「そんじゃ桂枝湯は?」
というお話。
・・・これこそ、まさに漢方薬の王様みたいな薬です。
出典はもちろん漢代、『傷寒論』でありまして、『傷寒論』のド頭に出てくるのが桂枝湯です。
また、北辰会会員の必携の書である『袖珍中医四部経典(※)』にも収録されている、清代の名医、呉鞠通の著書『温病条弁』も、ド頭に出てくる方剤はこの「桂枝湯」なのであります。
((※)・・・『黄帝内経素問』『黄帝内経霊枢』『傷寒論』『金匱要略』『温病条弁』がすべて簡体字で収録されている、何とポケットサイズの書。)
数千年の風雪に耐えてきた名方ですね☆
『傷寒論』中の桂枝湯掲載の条文を全てここに拾おうと思うと、あまりにも長くなるのでやめますが、これ自体にもとにかく非常に多くの使い方があり、
バリエーションも非常に多くある、漢方薬の王様です。
『金匱要略』にも、栝楼桂枝湯、白虎加桂枝湯、枳実薤白桂枝湯、鳥頭桂枝湯、柴胡桂枝湯と、様々なバリエーションや使い方が紹介されています。
・・・まあー、それだけ奥が深い薬なので、あまり簡単に語るのは語弊があるのですが、最もポピュラーな使い方は、カゼの初期に使う場合です。
しかし、麻黄湯とは違って、桂枝湯の場合は汗があります。
外から邪気が入ったことによって、体の表面における気血の流れのバランスが崩れて、本来出てはいけない汗が、ダラダラと出てしまっている状態です。
そこで、気血を調和させて、気の流れをよくし、結果的に邪気を散らし、汗を自然に止める薬、という理解が、最もポピュラーでしょう。
また、以前書いたように、桂枝湯は、服用した後に熱くて薄いおかゆ(熱稀粥)をすすれ、と書いてあることも有名ですね。
映画『レッドクリフ』で、感染症にかかった兵士に桂枝を煎じて飲ませているシーンがありましたが、三国志の時代から使われる、超有名な方剤です。
(映画の中でも孔明が言っていたけど、ああいう重篤な感染症が桂枝湯で治るというワケではないよ。)
この桂枝湯の様々なバリエーションについても、いつか気が向いたら書きましょうかね。
〇
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.04.07

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
最近のお話し
参照
昨日、小青竜湯に関して書いたので、今日は小青龍湯の元となる、超有名な漢方薬である麻黄湯についても、ついでなんで書いておきます。
麻黄湯というのも、『傷寒論』に出て来る方剤であります。
構成生薬は麻黄・杏仁・桂枝・甘草の4種であり、もちろん主薬は麻黄であります。
麻黄は桂枝と並んで、生薬の王様級に有名ですね。
この二つが入っている方剤を「桂麻の剤」と呼んで、実に様々なバリエーションがあります。
これの出典である『傷寒論』中には、
太陽病.頭痛發熱.身疼腰痛.骨節疼痛.惡風無汗而喘者.麻黄湯主之.
太陽與陽明合病.喘而胸滿者.不可下.宜麻黄湯.
太陽病.十日以去.脉浮細而嗜臥者.外已解也.設胸滿脇痛者.與小柴胡湯.脉但浮者.與麻黄湯.
太陽病.脉浮緊.無汗發熱.身疼痛.八九日不解.表證仍在.此當發其汗.服藥已微除.其人發煩目瞑.劇者必衄.衄乃解.所以然者.陽氣重故也.麻黄湯主之.
脉浮者.病在表.可發汗.宜麻黄湯.
脉浮而數者.可發汗.宜麻黄湯.
傷寒脉浮緊.不發汗.因致衄者.麻黄湯主之.
脉但浮.無餘證者.與麻黄湯.若不尿.腹滿加噦者.不治.麻黄湯.
陽明病.脉浮.無汗而喘者.發汗則愈.宜麻黄湯.
脉浮而緊.浮則爲風.緊則爲寒.風則傷衞.寒則傷榮.榮衞倶病.骨節煩疼.可發其汗.宜麻黄湯.
太陽病.脉浮緊.無汗發熱.身疼痛.八九日不解.表證仍在.當復發汗.服湯已.微除.其人發煩目瞑.劇者必衄.衄乃解.所以然者.陽氣重故也.屬麻黄湯證.
太陽病.頭痛發熱.身疼腰痛.骨節疼痛.惡風無汗而喘者.屬麻黄湯證.
陽明中風.脉弦浮大而短氣.腹都滿.脇下及心痛.久按之氣不通.鼻乾不得汗.嗜臥.一身及目悉黄.小便難.有潮熱.時時噦.耳前後腫.刺之小差.外不解.過十日.脉續浮者.與小柴胡湯.脉但浮.無餘證者.與麻黄湯.不溺.腹滿加噦者.不治.
太陽病.十日以去.脉浮而細.嗜臥者.外已解也.設胸滿脇痛者.與小柴胡湯.脉但浮者.與麻黄湯.
・・・と、至るところの条文に出てきます。(苦笑)
(なげえ~~ 読むのつれえ~~ (~_~;))
・・・まあ要するに、非常に汎用性の高い方剤であり、病が浅いところにあるものだけでなく、少し深いところに入っている場合でも、咳が出ていて、
汗が出ていないような場合などには非常に使える方剤であることなどが分かります。
体表を温め、一気に発汗させて治せるパターンのものをバシッと治す薬、と言えると思います。
ですので、すでに発汗しているようなタイプの人や、体質的、病理的に熱傾向の人、また、必要な水分(津液)や血液が不足しているような人が迂闊に使うのは危ない、となります。
因みに、ここでは詳しく述べませんが、『金匱要略』には、射干麻黄湯、厚朴麻黄湯、甘草麻黄湯という、麻黄湯のバリエーションも紹介されています。
因みにこの麻黄という生薬には、エフェドリンというアルカロイド(天然由来の有機化合物)が含まれています。
(単離に成功し、”エフェドリン”と命名したのは明治時代の日本人だとか。)
エフェドリンは、覚せい剤で有名なメタンフェタミンと分子構造がそっくりで、スポーツ選手などが競技前に服用したらドーピングで失格になっちゃうそうです。(^^;)
それだけでも、よく効きそうな感じがしますね。(笑)
しかし、単離できたからと言って、麻黄湯はエフェドリンが効くんだ、と考えるのではなく、麻黄・杏仁・桂枝・甘草の生薬4味からなる「麻黄湯」となっていて初めて、
『傷寒論』に書いてあるような効果が期待でき、様々なバリエーションが設定できるのだと思います。
そこを勘違いしない方がいいと「僕は」思っています。
〇
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.04.06

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
ここんとこ、
というお話を書きましたので、ついでなんで、最近花粉症でよく使われている「小青龍湯」についても触れておきましょう。
まあ湯液の話を、私のような実践で使っていない、ズブの素人がするのも実に僭越なんですが、あまりにもこれを処方されていて、しかも効果を感じていないと仰る患者さんを診ることが多いので、
僕自身の備忘録的な意味と、彷徨う患者さんのために、この薬に関する基礎的な内容を書いておこうと思います。
この薬の出典は後漢の時代、あの張仲景が書いた『傷寒論』であります。
小青龍湯は、有名な麻黄湯という漢方薬の加減方と言われます。
(麻黄湯も傷寒論に出てくる薬です。)
麻黄湯も最近、
「インフルエンザに効く!」
とか、
「キムタクが常備してる!」
とかいわれて、非常に有名です。
これについても、後で簡単にまとめておきましょう。
この麻黄湯は、よくカゼのひき始めに使われます。
小青龍湯は、もともとはカゼのひき始めの状態が改善せずに、なおかつ「水邪」が存在する時に使う薬、と、『傷寒論』に定義されています。
『傷寒論』内の条文では
傷寒表不解.心下有水氣.乾嘔發熱而欬.或渇.或利.或噎.或小便不利.少腹滿.或喘者.小青龍湯主之.
傷寒心下有水氣.欬而微喘.發熱不渇.服湯已.渇者.此寒去欲解也.小青龍湯主之.
傷寒表不解.心下有水氣.乾嘔發熱而欬.或渇.或利.或噎.或小便不利.少腹滿.或喘者.宜小青龍湯.
とあり、また『金匱要略』には
病溢飮者.當發其汗.大青龍湯主之.小青龍湯亦主之.
欬逆倚息不得臥.小青龍湯主之.
婦人吐涎沫.醫反下之.心下即痞.當先治其吐涎沫.小青龍湯主之.
とも書いてあります。
漢方薬の専門家でもない僕が、あまり難しい解説をしてもしょうがないし、そもそも出来ないので、要はこれらを簡単に言うと、表面に寒邪があって、
なおかつ心下(みぞおち)に水邪がつっかえてる場合に使う方剤であって、これとは違ったメカニズムで症状の出ている花粉症には効かない、
あるいは害になりかねない、ということになりますね。
また、たまたま合っていたとしても、この薬を服用して、表邪の存在、心下の水気の存在が除去、改善された後になっても、この薬を継続して服用していたら、
今度はまた違った病変に結び付く可能性もあります。
漢方薬はサプリメントなどではなく薬なのであり、素人考えでドラッグストアで買ってきてメチャクチャな使い方をしたりするのは、厳に気を付けたいですね。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.04.05

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
昨日、「牛車腎気丸」という薬という記事を書きました。
その時に、もう一種類、「治打撲一方」という薬の話にもなりました。
これはどうか。
これは実は、以前紹介した江戸期の医家、香川修庵先生(1683-1755)の創方だそうです。
墓マイラー 9 参照
ですが、真柳誠先生の研究によれば、「治打撲一方」という”名前で”文献に登場するのは、あの幕末から明治の漢方医、浅田宗伯先生(1815-1894)の
『勿誤薬室方函口訣(ふつごやくしつほうかんくけつ)』だそうで、ということは、この薬の名付け親は浅田宗伯になるそうです。
・・・まあ、個人的にはどっちでもいいんですが。(゚∀゚)
この薬の中に含まれる川骨(せんこつ)、樸樕(ぼくそく)という、活血化瘀の効果を持つ生薬は、呼び名からして日本独特であり、中国の処方に含まれることはないそうで、
そういう意味でもまさに日本製の漢方薬だそうです。
(もともとは戦国時代に傷や怪我を治療する秘伝の薬だったのを、香川先生がまとめたんだとか。)
(中国では川骨のことは萍蓬(ヘイホウ、コウホネ、カワホネ)というらしいが、『中医臨床のための中薬学』には載っていませんでした。。)
「治打撲一方」は、昭和になって、一貫堂の山本巌先生が紹介したことで、よく使われるようになった経緯があるそうです。
(今ではツムラのエキス剤になっています。)
これは中医学では血の流れを調える「理血剤」のグループであり、その中でも停滞した瘀血を取る「活血祛瘀剤」のグループで、その名の通り、
打撲や捻挫を治療する薬なんですが、応用的に骨折の後遺症などにも使われるようです。
さらに応用的には、経絡経筋が冷えて、瘀血が停滞した痛みなんかにも使われるそうです。
・・・ということは、外傷はともかくとして、気滞血瘀や瘀血性の疼痛に応用するには、
「経絡経筋に冷えがあり、気が停滞し、血も停滞している」
ということが診断できないとマズい、ということになります。
また、これを適切に運用するには、同じグループの有名な薬であり、現代でもよく使われる
「桃核承気湯」「血府逐瘀湯」「桂枝茯苓丸」「大黄䗪蟲丸」「温経湯」「抵当湯」
なんかとの使い分けができる能力が要求されるはずです。
まあ、治打撲一方に限って言えば、熱邪や湿邪の関与する痛みだったり、気虚や陽虚が関与するものに使ったらドボン、ということでしょうか。
漢方薬というのは、もちろんながら、東洋医学の生命観、疾病観に立脚して考案されたものです。
ここを無視して使用されているような現実があることは、実に残念に感じます。
〇
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.18

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
17日の日曜日は、目黒で行われた三旗塾オープン講座に参加してきました!!
この講座、当初の会場側のキャパは60名だったらしいですが、なんと参加者130名、ギュウギュウに詰めて、実にいい感じの熱気でした☆
(キャンセル待ちもずいぶん出たようです。)
やっぱ講演会場はすし詰めがいいね☆
この日の演者さんは、テレビ等のメディアで大活躍されている鍼灸師の若林理砂先生と、(一社)北辰会代表、藤本新風先生でした。
若林先生の取り組みは、非常に分かりやすく、人柄的にもストレートであり、しかもそれをご自身が楽しんでやっておられるなあ、という印象を受けました。
今後、ご自身の治療院を、数人の武術の指導者と組んで、薬店とトレーニングスペースを併設した治療院にするらしく、こういったやり方も、
今後の一つの在り方だろうと思います。
また、SNSなど、ネットを駆使して、体調不良を抱えている人などの「特定の条件の」人とどんどん繋がれる時代、若林先生のおやりになっているような、
「東洋医学的な健康相談を目的としたオンラインサロン」
や、
「メディアを駆使した情報発信」
をなさる鍼灸師の先生は、今後どんどん増えそうな予感を感じました。
(ただ若林先生も仰っていたように、そうそう簡単ではないと思いますが。。。)
オンラインサロン上の患者さんは極端な虚証が多いというのも、個人的には興味深いと思いましたね。
そして後半は新風先生による講義と実技。
多少の機材トラブルや準備不足なんかはありましたが、いつも通り、マズマズうまくいったと思います。
アンケートが楽しみですね。
終わった後は三旗塾の先生方と呑み。。。
最終的にはヒドイことになりました。(苦笑)
そして今日は東京衛生学園の謝恩会です。
昨日会ったメンバーと、また会います☆(^^)
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.08

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
ここまでのお話し
小建中湯について 2 参照
別にシリーズ化する気もなかったんだけど、書き始めたら何となく、
「あれも書いとこ、これも書いとこ。」
ってなって、徐々に続いてしまった、この「脾胃モノ有名漢方薬」シリーズ。(笑)
特に脈絡もなく、患者さんを診ていて、よく使われているものを書いています。
(こんなん書いてたら、キリがないね。。。)
もちろんながら、漢方薬というのは、鍼灸と同じように、芯となる流儀や考え方に基づいて、論理的整合性、一貫性をもって処方されるべきもので、
決して症状のみ、病名のみから場当たり的に処方されるものではないと理解しています。
だから僕は、全くの素人さんが、エキス剤とはいえ、ドラッグストアで簡単に漢方薬を購入できる現状、ネット通販で自分の症状から調べて入手しては、
サプリメント感覚で次から次に試しまくる現状にも、正直反対です。
もちろん、自分で鍼や温灸を買って適当に試すことにも、厳しいようですが反対です。
僕は鍼灸臨床家であり、畑は違いますが、今後も優れた漢方家の先生方と協調しながら、真面目に東洋医学をやっていきたいですね。(^^)
前置きが長くなりましたが、今日は「補中益気湯」です。
(これで一応いったん締めとしましょう。)
実は2013年の記事に、チラッと登場しました。
この方剤の出典はあの中国金元の4大医家の一人、李東垣(1180-1251)先生の『脾胃論』であり、『中医臨床のための方剤学』によれば、構成生薬は
人参9g、白朮9g、黄耆15~30g、当帰9g、柴胡3g、陳皮6g、炙甘草6g、升麻3g
となっています。
効能は補中益氣、昇陽挙陥、甘温除大熱であり、主治は気虚下陥、気虚発熱とあります。
まあ要は、”黄耆”という生薬を主薬とし、結果的には中焦の気(脾気)を補って、気を昇らせ、脱肛や子宮脱などの”中気下陥”の症状を改善させ、
場合によっては気虚発熱を改善するという目論見の薬です。
李東垣は『内外傷弁惑論(1247)』の中で、発熱には外邪が入って邪正闘争の結果発熱するものと、脾胃が弱ったことにって発熱するものがあり、
脾胃が弱った場合については甘温剤で脾胃をフォローすることによって清熱することが出来ると主張しました。
ここで重要なのは、熱証モノは脾胃を補えばいい、という理解ではもちろんなく、その熱証症状、所見が、”何によるものなのか”を鑑別診断できる物差しを身に付けることですね。
この物差しになるのが脈診、腹診をはじめとした”多面的観察”であります!!
患者さんが、
「先生風邪ひいたー。。熱が出たー。。。」
と、言っていたからといって、それがどういう病因病機によるものなのかに対する理解ですね。
意外と臨床上、脾胃を補うことによって熱証症状が取れていくことはあります。
アトピー性皮膚炎なんかでも、たまに経験しますね。
実際に漢方家の先生の中には、補中益気湯を使ってアトピーに効果を挙げておられる先生も少なからずおられるようです。
刮目すべき理論です。
〇
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.02
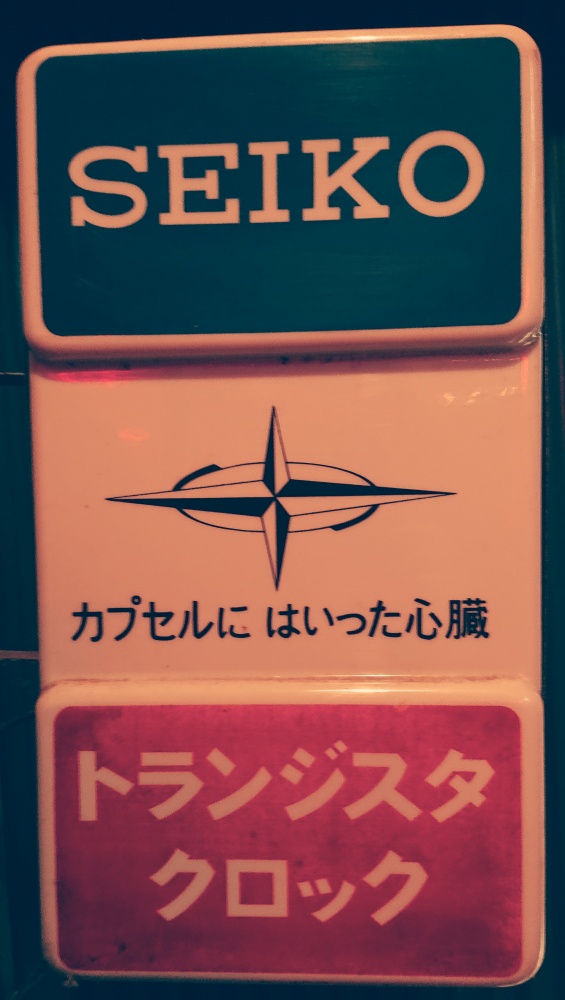
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
ここんとこ、
という記事を書きました。
ついでなんで、中焦(脾胃)モノを、もうちょっと書いときましょう。
単純に脾胃の病と言っても、寒熱虚実、他臓腑との関わり、色々あるんです。
それをきちんと分析して、きちんとした処置をしていかなかったら、治るもんも治りません。
今日は「安中散」です。
こないだ、これを処方されている胃痛、パニック障害の患者さんが見えました。
マズマズ効いていたようです。
これも出典は中国宋代、『和剤局方』であります。
『中医臨床のための方剤学』によると、
組成は肉桂(桂枝)4g、延胡索3g、牡蛎3g、小茴香1g、甘草1g、縮砂(砂仁)2g、高良姜1g、
効能は温中降気、止痛、
主治は裏寒の疼痛、
と、あります。
これは「温裏剤」のグループであり、『金匱要略』に出てくる、有名な「大建中湯」の附方(方意が類似している薬)として紹介されています。
要するに中焦を温めて寒邪を散らし、冷え痛みをとるのが方意な訳ですが、方意が似ているのに、組成はまったく違います。(苦笑)
ここが漢方の面白いところなんでしょうね。
・・・まあ、鍼灸もそうですね。
同じ効果を狙って、全然違う経穴に、全然違う鍼灸をすることは、日常的にあります。
「大建中湯」の場合は、脾胃+主に肺腎を意識しながら、急いで冷えと上逆を取りにいく方剤であるのに対して、「安中散」は脾胃+主に肝を意識して、
長期的な冷えに対して、”理気”というアプローチをかけていますね。
鍼灸でも、大建中湯的な効果を狙うのと、安中散的な効果を狙うのとでは、配穴から手技から違います。
・・・ところで「大建中湯」は、消化器外科でエラク使われるようです。
これにも触れときましょうか。
(キリがねえなー(;’∀’))
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.02.21

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
こないだ、患者さんで、
「生理痛にノニジュースが良いと聞いて、飲むようにしたら痛み止めを使わないでもいられるようになった!」
という人がいらした。
この手の話は、臨床をやっているとゴマンと出会うが、バカにしてはならないと思っています。
(藤本鉄風先生の教えですね。)
・・・今回も、ほう、と思って、少し調べた。
清明院から歩いてすぐのところに、巨大なビルが建っている「ノニ」。
こないだ話題になった「青汁王子」じゃないけど、こういった健康食品産業ってのは、スゴイもんだね。(゜o゜)
新宿にビルが建つなんて、鍼灸院ではとても無理っす☆
10代の頃から、朝から晩まで勉強して、臨床して、休みの日は勉強会行って、やっとこさっとこ学術を身に付けて、それでもやっとこさっとこメシが食えているくらいなのに、
とある健康食品を開発して、上手に宣伝して、通販で全国に売ったら、新宿に巨大なビルが建つ。。。
これが社会の現実です。(;’∀’)
・・・まあいいっす、僕は僕で、大都会新宿の片隅で、コツコツとやります。(`・ω・´)ゞ
さてこの「ノニ」ですが、東南アジアからオーストラリアにかけての太平洋熱帯地域全域に生育する常緑低木または小木だそうです。
日本では沖縄に「ヤエヤマアオキ」という和名の自生種があるそうで、古くから果実や根や茎が薬用に使われてきた歴史があるそうです。
まあ、「ノニ」の効果については、色んなサイトで、色んなこと(効果効能)が実に景気よく書かれています。(苦笑)
・・・でもまあ、こちらのサイト様に書かれているように、科学的根拠は不十分、という、いつものやつではないでしょうか。
ただ、冒頭にも述べたように、「科学的根拠が不十分」だから大したものではない、と即断するのは違う。
因みにノニは、morinda属の植物なんだそうだが、同じmorinda属の植物を使う生薬に「巴戟天(はげきてん)」という生薬があります。
毓麟丸(いくりんがん)、巴戟丸(はげきがん)、金剛丸(こんごうがん)といった、聞きなれない処方に使われるようで、中薬学では「補益薬」のグループで、特に「助陽薬」に分類されます。
(まあ、陽気を補うグループです。)
巴戟天は根っこの部分を使うらしいが、腎陽虚+寒湿邪の女子胞の冷えからくる不妊症や生理痛、生理不順などによく使う生薬だそうで、
ノニもこれと似たような効果が期待できるとすれば、生理痛が取れたというのも納得できる。
しかし、熱帯地域にある植物で、冷えを取るとは。
清熱にいきそうなイメージを持っていましたが、陰虚熱、湿熱には禁忌だそうです。。。
意外とこういう、患者さんのいう、健康食品で奇効が得られたという話が、鍼灸治療や、養生研究の役に立つことがある。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.02.18

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
眠れない患者さん、よくいます。
安定剤、導入剤に頼っているケースが大多数。
暫く使っていると、効かなくなってきたのでと、分量を増やしたり、より強い薬に変えていく。
雪だるま式に増えていく。
・・・そうなる前に、鍼灸をお勧めしたい。
不眠症は、東洋医学では「不寝(ふしん)」と呼んだりする。
明代の大名医、張介賓(張景岳 1563-1640)の『景岳全書』(1624)に曰く。
不寝はただ邪正の二字すなわちこれを尽くすと知るなり。
神が安定すれば眠れる。
神を不安定せしめるものは邪の擾か、営気の不足。・・・
〇
と、単純明快に喝破する。
また、清代の呉鞠通(呉瑭 1736-1820)の『温病条弁』(1798)に曰く。
不寝の原因は甚だ多い。
陰虚で陽納出来ないもの、陽亢で陰に入れないもの、胆熱、肝気(肝用)不足、心気虚、心陰虚、心血虚、蹻脈不和、痰飲擾心。
〇
と、多数のパターンを上げております。
どっちも正しいと思うが、張景岳先生の「所詮は虚実」という斬り方が個人的には好き。
標本主従あるけど、心神の関与はあると診た方がいい。
そして、蹻脈と心神、肝胆と心神に関して、生理と病理を整理するべき。
その上での「所詮は虚実」。
【参考文献】
『症状による中医診断と治療』燎原出版
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.02.12
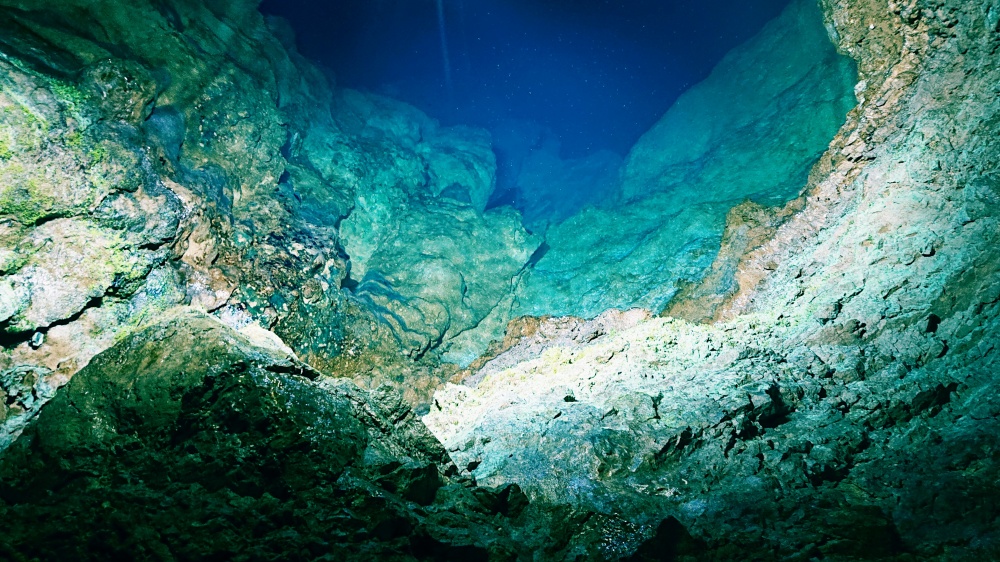
清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
2.10~11の二日間は、熱海の温泉旅館「和風館」で行われた(一社)北辰会、冬季研修会「順雪会(じゅんせつえ)」に参加してきました!!
これまで、何度となくこのブログでも煽ってきましたが、鍼灸師の先生を中心に、医師、薬剤師の先生も含め、結果的に約100名の参加者が全国から参加され、
盛会裏に終了いたしました!!
今回、直前に予想外に風邪をひいて声が枯れていたので、初日の講義「B試験解説」、その後の実技指導、夜の飲み会、二日目の実技指導と、
声がもってくれるかどうか、正直心配でありましたが、前日の2.9の夜に藤本新風先生と油谷真空先生に、初日、二日目と連続して藤本蓮風先生に超豪華三日連続治療していただき、
二泊三日の間、あんなに喋りまくっていたのに、むしろ来た時よりも全然治りました。(笑)
・・・いやー、あらためて鍼はスゴイ!!
やっぱり、自分が本当に調子の悪い時に、先輩の鍼を受けないとイカンですね。
大変勉強になりました。<m(__)m>
近々、北辰会の公式ブログでも報告があることと思いますが、年々この研修会の内容は充実してきており、今回も非常に成功したと言っていいと思います。
蓮風先生の講義も感動的でよかったです。
天国の中村順一先生にも届いているでしょう。
アンケートの集計結果を待ちたいと思います。
・・・さて、来年はさらにブラッシュアップして、北辰会を代表するイベントに成長して欲しいと思います。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.07.08
2016.05.09
2016.04.12
2016.04.28
2015.06.04
2012.12.23
2014.02.17
2014.04.26
2025.04.01
2025年 4月の診療日時2025.03.13
2025年2月の活動記録2025.03.01
2025年 3月の診療日時2025.02.06
2025年1月の活動記録2025.02.01
2025年 2月の診療日時2025.01.21
順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10
2024年12月の活動記録2025.01.02
2025年 1月の診療日時2025.01.01
謹賀鍼年!!2024.12.28
年内診療終了!!2024.12.14
2024年11月の活動記録2024.12.01
2024年 12月の診療日時2024.11.07
2024年10月の活動記録2024.11.01
2024年 11月の診療日時2024.10.10
清明院15周年!!!2024.10.09
2024年9月の活動記録2024.10.01
2024年 10月の診療日時2024.09.19
2024年8月の活動記録2024.09.01
2024年 9月の診療日時2024.08.03
2024年7月の活動記録2024.08.01
2024年 8月の診療日時2024.07.10
患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05
2024年6月の活動記録2024.07.01
2024年 7月の診療日時2024.06.05
2024年5月の活動記録2024.06.01
2024年 6月の診療日時2024.05.10
2024年4月の活動記録2024.05.01
2024年 5月の診療日時2024.04.13
(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02
2024年3月の活動記録2024.04.01
2024年 4月の診療日時2024.03.14
2024年2月の活動記録2024.03.01
2024年 3月の診療日時2024.02.15
2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04
3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03
3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02
2024年1月の活動記録2024.02.01
2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01
2024年 2月の診療日時2024.01.11
2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05
診療再開!!2024.01.01
2024年 1月の診療日時2023.12.30
2023年、鍼療納め!!2023.12.21
(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01
2023年 12月の診療日時2023.11.26
患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25
患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22
12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21
今週からの講演スケジュール2023.11.16
日本東方医学会学術大会、申し込み締め切り迫る!!