お電話
03-6300-0763
10:00~21:00(完全予約制)
2011.04.08
我々鍼灸師には、「インターン制度」というのがない。
つまり、国家資格を取得したら、あとは野放し状態だ。
(まあ仮にインターン制度があったとしたって、インターン制度が終わりゃあとは野放しなんだから結局同じことなような気もするが・・・。)
国も鍼灸の方法論についてまでは、ガイドラインなんて設定してないから、各人が各人の理論でやりたい放題、
それぞれがそれなりに効果を挙げているという、まさに玉石混交状態がこの業界だ。
・・・この辺の業界の現状については、以前このブログに書いた。
カテゴリ 「鍼灸と保険」 参照
だから清明院みたいに1本しか鍼を打たない治療院もあれば、1、2時間かけて全身に100本近く鍼をする治療院もある。
あとは鍼に電気を流してみたり、モグサをくっつけて火をつけてみたり、てんでバラバラ・・・。
こういう中で、やり方はどうあれ「本当に治せる」「確かな」技術力を持った先生の治療院に勤め、その技術の一端を教わることが出来たら、それはかなりラッキーだ。
奇跡に近い、と言ってもいいと思う。
しかしそれでも、初めて患者さんに鍼をするときは緊張するものだ。
結局鍼をするのはその先生じゃなくて、自分自身なのだ。
うまくいかなくて、失敗することもあるかもしれない。
患者さんに嫌われてイヤな思いをすることもあるかもしれない。
職場の院長に迷惑をかけて怒られることもあるかもしれない。
でも歯を食いしばって頑張るしかない。
「失敗は成功のマザー」なのだ。
みんなが通る道なのだ。
愛すべき読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
清明院に皆様のお力を!<m(__)m>
2011.01.30

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
「腎(じん)」ってなんですか?(その1)
「腎」って何ですか?(その2)
「腎」って何ですか?(その3)
「腎」って何ですか?(その4)
「腎」って何ですか?(その5)
「腎」って何ですか?(その6)
「腎」って何ですか?(その7)
「腎」って何ですか?(その8)
「腎」って何ですか?(その9)
「腎」って何ですか?(その10)
・・・さて、そろそろ「腎」シリーズ、ラストになります。
これまで色々と書いてきましたが、「腎」というのは、五臓六腑の中でも特に重要な臓であります。
患者さんが訴える、様々な症状の根本中の根本になっていることも少なくありません。
したがって病を根っこから治療しようと考えた時、治療対象になることも多い臓です。
東洋医学の言う五臓六腑というのは、どれが欠けてもダメ、全体のバランスが重要、という風に考えますが、その中でもとりわけ重要なのはどれかといえば、
私は「肝・脾」・腎」の3臓であると考えています。
(まあここは、考え方によって多少分かれるところでしょうけども。)
ともかく、人間の生殖をつかさどる腎の臓・・・。
近年増加し、問題になっている不妊症や不育症、先天性の病なんかにも、大きく関与することが多いのです。
また、漫画などで描かれる、高齢者のトレードマークといえば「白髪」と「入れ歯」と「曲がった腰」ですが、これらにも「腎の臓」は大きく関わります。
☆「腎」と「髪」と「歯」
以前、髪の栄養である「血」と大きく関わるのは「肝の臓」である、というお話をしました。
しかし髪の栄養には、「腎」も大きく関わります。
なぜならば東洋医学には、
「肝腎同源(かんじんどうげん)」
という有名な言葉があります。
・・・コレはどういう意味かというと、腎が蔵する「精(せい)」は、体の状況に応じて「血(けつ)」に変化し、反対に肝が蔵する「血」が、「精」に変化する場合もある、
という、「精」と「血」は同根で、もともと同じものである、という考え方であります。
つまり、「血」が足らなくなると「精」が変化して補い、その逆パターンもある、ということです。
つまり、
「血の余り」
と言われる「毛髮」には、「肝」と「腎」が大きく関わる、という風に考えるのです。
(これを”精血同源(せいけつどうげん)”と言ったりもします。)
そしてさらに、東洋医学では「歯」のことを、
「骨の余り」
と呼びます。
「歯」というのは実際に、上あごと下あごの骨にガッチリとくい込んでいまして、骨を基礎として伸びてきます。
まさに、成長過程からも、見た目も見るからに「骨の余り」なんですが、その「骨」と、その中にある「骨髓」をしっかりとした良好な状態に保つ働きを持っているのが、
まさに「腎の臓」なのだ、ということです。
・・・ということは、「髪」と「歯」の状態というのは、そのままその患者さんの「腎の臓」の状態を示すことが少なくないのです。
小さい頃から虫歯が多いとか、50代後半で総入れ歯になったとか、出産したら歯がボロボロになったとか・・・、小さい頃から骨折しやすいとか、
中年期から背骨が変形して姿勢が曲がってきたとか・・・、若いうちから白髪が多いとか・・・、などなど、自分を考えても、周りの人を思い浮かべても、
思い当たる方が多いのではないかと思います。
・・・信じられない方もいるかもしれないけれども、高齢者で髪が真っ白の方が、鍼治療を始めてから、黒い髪が生えてきた、という事例を、僕は何度も経験しています。(笑)
まあ要は、
「腎の臓」をいい状態に保つことによって、高齢者はいつまでも若々しくいられるし、
若者は若者らしく、健全な人生を全うすることが出来るのです!
そして、東洋医学は、それの大きな助けになることが出来るのです!
・・・ということで、「腎の臓」シリーズ、ひとまず終了。
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2011.01.11

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
3月に、(一社)北辰会関東支部定例会基礎コースにて、
「奇経八脈総論(きけいはちみゃくそうろん)」
というテーマで朝から2時間、講義をやらせていただきます。
「正経十二経」に対して、「奇経八脈」・・・。
・・・まあ、鍼灸師なら誰でも知ってて、しかもみんな興味深いテーマなんです、コレ実は。
な~んか、いわゆる「秘伝」的な、秘密がある感じがするんですよね、コレ。(笑)
また、興味深いというだけで、意外と細かい内容については全然知らない、という先生が多いのも、事実ではないかと思います。
なぜ、みんな興味深いのかというと、ベテランの先生や、この業界で有名な先生の臨床をみると、みんなこの、「奇経八脈」に関係する経穴を多用して、
難しい病から簡単な病まで、自在に治療していることが多いんです。
(一社)北辰会代表である、藤本蓮風先生の治療も、その点、例外ではないように思います。
・・・ということで、僕も学生時代から、これには随分興味を持ちました。
何か秘密、タネがあるような気がしてネ。(笑)
そして、色々調べました。
すると、なるほど、確かに謎めいた部分はあるようです。
それも非常に重要な部分が、です。
歴史上、「奇経八脈」がまとまった形で登場するのは、前漢の時代に著されたとされる鍼灸の聖典の一つ『難経』です。
そして、その八つの特殊な脈を治療する方法として、八つの経穴が提示されるのは、だいぶ時代が下って、元の時代の『針経指南』です。
『難経』にも、”なぜこの八つなのか”とか、『針経指南』にも”なぜこの八穴なのか”とか、という理由の詳細までは、書かれていません。(苦笑)
初めて言った人の意図や理由がハッキリと明言されていない以上、理論のもともとの根拠が明確にはなりません。
ですので、こうなんじゃなかろうか、ああなんじゃなかろうかと、実践に基づいて「仮説を立てること」が極めて重要だと思います。
つまり、奇経八脈の登場以降、現在までの歴史的変遷を踏まえた上で、実際の臨床に裏打ちされた、「自分なりの見解を持つ」ことが重要なのではないでしょうか。
(机上の空論ではなく、実地臨床に基づいた、です。)
(一社)北辰会からは、先日の蓮風先生のブログにもあったように、近い将来書籍が出版されるとのこと。
鍼狂人の独り言 奇経八脈1 参照
我々にとって、大いに参考になる本が出るはずです。
・・・まあ、いずれにせよ大変興味深い。
学生時代から、今日でも非常に興味深い。
日々臨床を、やればやるほど、ここは興味深い。(笑)
・・・「正」と「奇」という考え方は、古くは紀元前、孫武(そんぶ)という人が書いた、兵法書として有名な『孫子(そんし)』の中に出てきます。
臨床家にとって、病治しとはまさに戦のようなものなんです。
患者さんに巣くう病魔との、ガチンコの、待ったナシのタイマン勝負です。
ぼやぼやしてたら、取り返しがつかないぐらいボコボコにされます。歯を折られます。(苦笑)
命を取られることすらあるでしょう。
だから兵法書の考え方が役に立つのは当たり前です。
蓮風先生もよく、『孫子』の「奇」と「正」について、桶狭間の戦いを例に出して説明されます。
いうまでもなく、今川義元の2万5千の兵に対して、織田信長はわずか2千余りの兵で奇襲攻撃を仕掛け、見事に討ち取り、天下統一のきっかけを作ったと言われる、
よくドラマにもなる話です。
(・・・まあ、実際は奇襲じゃなかったとか、諸説あるようですが。)
・・・ともかく、その『孫子』兵勢の中に、
「およそ戦(いくさ)は、正を以(もっ)て合い、奇を以(もっ)て勝つ」
と、有名な文言が出てきます。
明徳出版社『孫子』田所義行 P120 参照
(『孫子』は最近、ビジネスマンのための人生哲学書みたいな感じで、色々な解説本、解釈本が出ていますね。コンビニなんかによく置いてありますな。スゴイことだと思います。(゜o゜))
さらにこの「正」「奇」の考え方は、『孫子』の少し後、孫臏(そんぴん)という人が書いた『孫臏兵法』という書の中にあったと言われていた、「奇正篇」の中に、
「奇、発すれば而(すなわ)ち正と為るも、其の未だ発せざる者は、奇なり。奇、発して報ぜられざれば、則(すなわ)ち勝つ」
と出てきます。
(因みに最近の研究では、『奇正篇』は『孫臏兵法』とは別の書物とされているんだそうです。)
ちょっと難しい文章なんですが、こちらの論文を参考にさせていただきました。
ここでは、勝つための方法論としての「奇」の重要性が述べられています。
まあ、『孫子』『奇正篇』、コレら2つから分かることは要は、戦に勝つためには「奇」は必要だけれども、はじめから「奇」をてらってそれを行動に移しても、それじゃ相手にとっては「正」になるんだから、
しょせん勝てやしないよ、ということでしょうか。
(簡単に言い過ぎか?(笑))
ここから、”奇”はしょせん”奇”、あくまでも”正”あっての”奇”なのだ、ということが分かります。
しかしながら、逆に言えば”奇”なくしては”正”もないことも事実。
「奇」は「正」を生み、そして「正」もまた「奇」を生む・・・。
コレまさに
「如環之無端」
なのであります。
「如環之無端」という言葉 参照
まあ結局、正攻法ばっかりで基本に忠実、って感じでやってても負けるし、最初から奇をてらって、奇襲戦法ばっかりでも負ける、だから奇正を熟知して、臨機応変にうまくやったやつが一番勝てる、
って話で、耳の痛い、まさに臨床そのものみたいな話です。(苦笑)
・・・ですから、「奇経八脈」を理解することというのは、「東洋医学的治療戦略」を考える上で、実は大変奥が深い世界なんです。
僕ごときにどこまで表現できるか分からないけども、3月、頑張りま~す。(笑)
来る人は、お楽しみに~♪
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2010.10.09
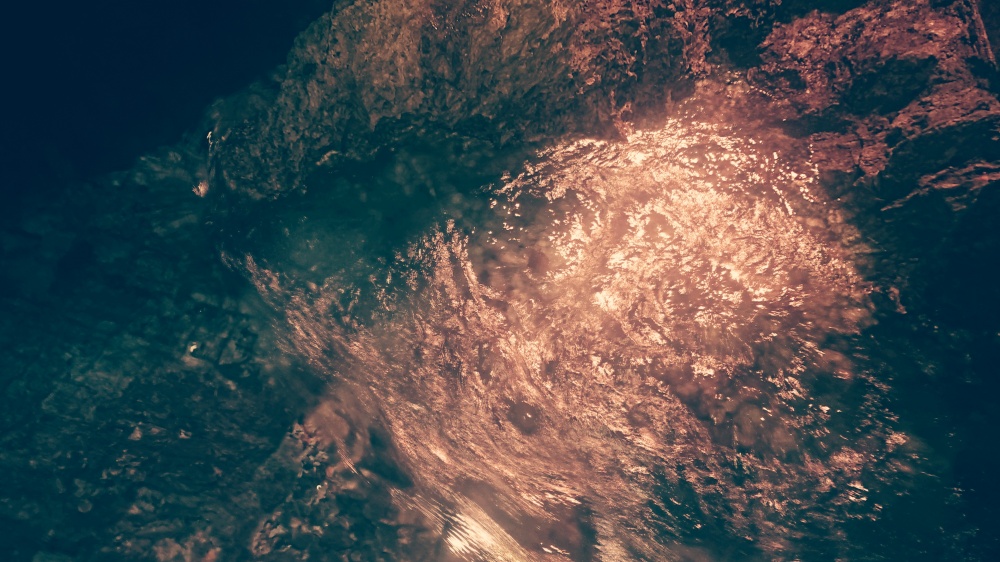
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
前回までのお話・・・
「肺」って何ですか?(その12)
「大腸」って何ですか?
「大腸」って何ですか?(その2)
「大腸」って何ですか?(その3)
「大腸」って何ですか?(その4)
前回までで「大腸の腑」の働きについて、重要なことは述べました。
(他のに比べると少ないっしょ?)
今回は、ではその大腸を病むと具体的にはどうなるのか?というお話です。
☆「大腸の腑」の異常
まず重要なのが、「便秘」、「下痢」等の、分かりやすーい、「お通じの異常」ですわな。
コレが起こっている、ということは、もし病的なものであれば、病変の「場所」としては「大腸の腑」ということになるけれども、これを治療する上では、
これが起こった「メカニズムに対する理解」が極めて重要です。
色々と問診し、体表観察し、その症状の原因を特定しなかったら、治療なんて出来るはずありません。
だから、「便秘には〇〇!」なんていうのは、土台、あり得ない話なんです。
そんなんで治ったら誰も苦労しやしません。(苦笑)
☆「大腸の腑の経絡」の異常
五臓六腑には、それぞれと関わりの深い経絡が存在し、全身をくまなく巡っています。
今はコレについて一つ一つ詳しくは述べませんが「大腸の腑」にもそれはあります。
「経絡」については「経絡(けいらく)」って何ですか? 参照
「大腸の腑」の経絡は、
手の人差し指、手首、肘、肩、首筋、歯、鼻、ほっぺた、目、
などを通っています。
これらの部分の異常(例えばテニス肘、五十肩、肩こりなどなど..)は、意外と「大腸の腑」の異常と関係があることがあります。
例えば、五十肩で痛くてしょうがない、と言う人に、よくよく話を聞いてみると、そういえば肩が痛くなる少し前から便秘気味だった、なんていうことがあるんです。
このように、東洋医学では、一見、症状とは関係のない部分に鍼やお灸をしたり、症状とは関係のなさそうなことをあれこれと問診したりするのは、こういう、
「臓腑の異常」
と、
「経絡の異常」
を常に結び付けて考えているためなんです。
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2010.08.06

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
「胃」って何ですか?
「胃」って何ですか?(その2)
「胃」って何ですか?(その3)
「胃」って何ですか?(その4)
「胃」って何ですか?(その5)
「胃」って何ですか?(その6)
「胃」って何ですか?(その7)
「胃」って何ですか?(その8)
☆胃が関わる範囲
さて今日はいよいよ、東洋医学的な「胃の腑」を病むと、実際にどういうことが体に起こるか、という問題です。
でも、これを細かく解説したら、難しくなるし、教科書みたいになっちゃうから、しません。概要を述べます。
・・・一般的には、西洋医学的な「胃の病気」と言うと、胃炎とか、胃潰瘍とか、胃癌とか、要は「胃〇〇」という病名が多いと思います。
これらは基本的に内臓の一部である胃(stomach)の形態的な異常、腹部の消化器症状が主な診断ポイントです。
しかし東洋医学では違います。
「全然」違います。(笑)
「胃の腑」が関わる範囲は「胃」そのものや腹部の症状だけではありません。
ちなみにこれは「胃の腑」以外の他の臓腑でも、全て同じことが言えます。
いつも言うように、東洋医学では、ある臓腑、ある部分、というのは、「あくまでも全体の中の一部にすぎない」という観点をどこまでも外さないため、
常に全体を意識しながら診察診断していきます。
そして、一見まったく関係ない部分(例えば手足や顔)の異常でも、常に五臓六腑と関連付けて考えるのです。
その「五臓六腑」それぞれと「一見関係ない離れた部分」とを結びつけるモノこそが「経絡(けいらく)」と呼ばれるものなのです。
・・・まあ、あまり難しい言い方は嫌いなので、簡単に言いたいと思いますが、この「経絡」というものを介して、「胃の腑」が関わる体の各部分というのは、非常に広範囲にわたります。
まず顔面(特に目、鼻、口、歯)から始まり、のど(首の前面)、胸(乳房、心の臓も含む)、お腹、背中、陰部、股関節、膝、足首・・・と、ほぼ全身各所に関わります。
特徴は、全身なんだけど特に「前側」の異常に大きく関わる、ということです。
なので当然、上記の各部分の病には「胃の腑」の異常から起こるものが多々あり、「胃の腑」を調えることによって治っていくものがある、ということです。
だから例えば西洋医学的な目や鼻の病気、のどや乳房の病気の中には、「胃の腑」に着眼して治療することにより治すことが出来るものがある、
という発想になる訳です。
・・・これが、発想だけで終わったらつまんないけど、実際にそうなるから、スゴイ訳です。
分かっていただきたいのは、例えば花粉症で鼻がつまって目が痒い、なんて時に、足に1本、「胃の腑」を調整する鍼を打ったら、症状が劇的によくなって、その先生から、
「あんたは胃が悪い!」
なんて言われたとして、この場面て、患者さんとしては意味分からんと思うけど、そこにはこういう理論がちゃんとあるんだよ、ということです。
次回に続く
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2010.07.01

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話・・・
「脾」って何ですか?(その1)
「脾」って何ですか?(その2)
「脾」って何ですか?(その3)
「脾」って何ですか?(その4)
「脾」って何ですか?(その5)
続きいきます!!
☆脾と口とくちびる
脾の働きは口の機能と関係が深いです。
(「喋り」という意味よりも、この場合は唇も含めた、口腔粘膜全般の機能、と考えて下さい。)
例えば卑近な例を挙げれば「口角炎」や「口内炎」、これらは経験したことがある人も多いんじゃないでしょうか。
僕も普段患者さんに聞かれることがあります。
「口内炎や口角炎がよく出来るんだけど、どうして??」
僕は大体、
「胃腸の働きが弱っているからだよ。」
と答えます。
・・・これは実は、
「それはねー、内外の複雑な原因があいまって、五臓六腑の中の、消化機能をつかさどる”脾”という臓が機能低下をきたした結果、流注の面、
生理機能の面から関わりの深い口唇に異常が出たんだよ。」
という難し~い言い方の回答を(笑)、省略して簡潔に述べている訳です。
こんなことを実際の患者さんに言ってたら、途中で寝られちゃいます。(笑)
ここでもし西洋医学の医師であれば、
「それはビタミンの不足です。」
な~んて言って、ビタミン剤を処方するかもしれませんよね。
ここにも、東西の視点の違いが見て取れます。
要するにビタミンを吸収する人間側の消化機能を問題視するか、摂取ビタミンの絶対量を強引に増やすことによって強制的に治そうとするか、という違いです。
どちらが人体に優しいか、また、長い目で見た場合に、どちらが問題が起こらなそうか、普通に考えりゃ誰だって分かります。
僕なんかはそもそもこんな飽食の時代に、「ビタミンの絶対的な不足」という状況なんて、果たして起こるんかしらー?と思っちゃいます。
もし仮にそれが起こってたとしたって、それ以外に過剰なものがあってそれが消化管粘膜に負担をかけてる場合、それを控えるだけで済む場合もありうると思います。
・・・ま、いいけど。(苦笑)
またこの他にも、「味覚」にも脾の働きが関与します。
風邪をひいて鼻がつまって味が分からなくなる、という経験は、誰もがしたことがあると思いますが、あれなんかは脾の弱りが関わってることが多いです。
脾は、口腔内を津液(生理的な水分)で潤し、舌や歯など、口腔内に存在する重要なものが十分に機能を発揮できるようにサポートする役目も持っているのです。
つまり、脾がしっかりしていると、口の中や口周辺は適度に潤い、その機能を十分に果たすことが出来るんです。
以前、舌には心の臓が深く関わる、というお話をしましたが、人間のあらゆる機能というのは、このように様々な臓腑がうまく協調することによって初めて成り立っている、と東洋医学では考えます。
これらの「どこがどう」アンバランスを起こしたかを見抜き、治療するのが東洋医学的な治療なんです。
次回に続く
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
2010.03.21
この間、いいコメントをいただきましたので、「鍼灸と保険」というテーマで何回かに分けて書こうかな、と思います。
(そういうことにも目を向けていかないとね。現実は大事です。目をそらさずに行きましょう!)
まず初めに、今現在、日本は言うまでもなく「国民皆保険制度」というものを採用しています。
これのお蔭で、前年の収入に応じて1~3割の負担金で国民誰でもが低額で医療を受けることが出来ます。
(皆さん持ってますよね?保険証。)
仮に収入がなくても、生活保護制度、後期高齢者医療制度等によって、その権利は守られますし、病気によっては全額公費負担になる制度もあります。
とても弱者思いの、いい制度ですよね。
しかしこれは、「保険医療機関」での治療がメイン(というかほとんど)です。
つまり、国家資格である「医師免許」や「歯科医師免許」を持った医師が営業している、病院、医院、診療所、クリニック、歯科医院での治療に関して、
保険者(国や保険組合等)から治療費の大部分(7~9割)が支払われるわけです。
あと一部、柔道整復師がやっている接骨院、整骨院でも保険が使える、という認識があります。
しかしこれは正確に言うと、接骨院の場合は原則として、一度窓口で治療費を全額(10割分全額)払って、自分の保険負担割合との差額分を、
患者さん自身が、自分で保険者(例えば国保なら区役所)に請求する、という方法をとるものです。
(あくまで「原則」としてね。)
しかしそれだと、一時的にでも患者さんの負担が大きくなりますので、多くの(というかほとんど全ての)接骨院では、「受領委任」といって、
保険者への差額の請求手続きを接骨院が代行するため、窓口では一部負担金のみをいただく、という形をとっています。
接骨院に治療に行ったことのある方は、申請書にサインを求められた経験があると思います。
これは、上記の手続きを接骨院さんの方に任せますよ、という確認なんです。
これにより、接骨院、整骨院では保険が使える、という認識が国民に浸透しています。
もう一つ言うと、接骨院で保険が使えるのは「骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷の5つの外傷(ケガ)のみ」についてです。
最近、慢性の腰痛や肩こり、単なる疲労感などに対する不正な保険請求が問題になっていますね・・・。
(逮捕者も全国に出ています)
ではいよいよ、鍼灸の場合はどうかというと、一応、保険は使えます。
・・・が、なぜかほとんど全然、使っている鍼灸院ありませんよね?
これはなぜかというと、保険を使って鍼灸を受けるためには、「医師による同意書」というものが必要になることと、保険制度においては、
一回の治療費がかなり低く設定されていること(総額でなんと1500円程度!)が理由になると思います。
しかも、保険適用になる症状として、「腰痛、頸肩腕症候群、リウマチ、五十肩、神経痛、頸椎捻挫後遺症」という、たった6つの疾病に限定(!)されており、
なおかつ、ひと月の治療回数、治療開始から終了の期間に至るまで、全て同意書を書いた医師が決定します。
さらには、上記6つの疾病を、病院と鍼灸院で併療(同時に治療)することは認められていません。
これまでに、患者さんがそのことを知らずに、同じ疾病で医院と鍼灸院に同時にかかってしまって、鍼灸院に「だけ」保険者から治療費が支払われなかった、
なんていう恐ろしい事例もあったようです。
しかも、今では撤廃されましたが、つい最近までは、鍼灸の治療回数には、なぜか法的に制限(ひと月10回までだったかな?)があり、
とてもまともに商売できるような仕組みではございませんでした。
そのため、保険専門の鍼灸院というものはほとんどなく、積極的に保険を使っている鍼灸院は、単純にすぐ隣にある医院と業務提携していたり、
単純にそこの鍼灸院の院長の親や親戚が医師であったり、という特殊な場合以外は、なかなか導入しにくいのが現状です。
「・・・あのさー、これ、なんか不公平じゃない?」
と思います。
さも日本という国に、保険制度に、鍼灸なんて効かない、嫌いじゃ、滅びよ!と言われているような気ィすらします。(苦笑)
しかも前回のブログにも書いたように、患者さんからは怪しい、痛そう、熱そう、恐いなんて言われます。(苦笑)
なんで、こんなことになるんでしょう。僕ら一生懸命やってるつもりなんだけどなー・・・。
毎日毎日、睡眠時間、遊ぶ時間を削って、鍼の本を読み、休日は勉強会にいき、知識、技術を少しでも高め、患者さんの健康に少しでも寄与しようと頑張っているのは、
鍼灸の学術を最大化するためであって、こんな扱いを受けるためじゃない!
・・・とかって、卑屈になったこともあります。でも冷静に考えれば、こうなるには、それなりの理由、いきさつがあったはずです。
(次回に続く)
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
清明院に皆様のお力を!<m(__)m>
2010.01.15
前回に続いていきましょう。
2、「鍼灸師みたいな低学歴の連中に体を診てもらおうとは思わない。」
コレなんですが、最初読んだとき、
「へ~、まだ日本にこういう考えの人がいるんだ~。」
と、妙に感心してしまいました。(苦笑)
学歴社会(高学歴=無条件にいい!という時代)なんて、一体いつの時代の話なんでしょうか。
・・・まあでも、そう言われたら仕方ないです。正直ね。
「ではどうぞよしなに。有名な大学病院の教授さんのとこにでも行ってください。」
です(笑)
・・・でもね、治療というのは「技術」の世界ですので、どんなに輝かしい高学歴があっても、手先の不器用な人には細かいオペなんて出来ないでしょうし、鍼灸もそれは同様です。
また、学問(理論)の力で完璧に、理路整然とその患者さんの病気を分析しきれたとして、それで治らない病気があるからみんな困ってるんじゃないの?とも思います。
確かに、西洋医学を実践されている、医師免許をお持ちの先生方というのは、医大の難関入試に合格し、国家試験に通り、なおかつインターン制度を消化した、
いわばエリートの方々です。
(前述の、「学歴社会」における勝ち組、と言っていいでしょう。)
それと比較して、鍼灸師というのは、現在国家資格ではあるけれども、国家資格化されてからまだ20年ぐらいの、若い国家資格です。
3年制の専門学校か、4年制の大学に通ったのち、国家試験に合格すれば「鍼灸師」を名乗り、開業することが可能ですが、インターン制度も特にありません。
僕の学生時代でも、クラスの人々の過去は様々で、有名大学出身者から、高校新卒者、脱サラ組、老後に細々とやれれば、とお考えの年配の方などなど、
まさに玉石混交状態でした。
しかも、2000年頃、小泉政権の頃には、規制緩和で、全国的に養成学校(専門学校)が爆発的に増えまして、毎年1000人程度だった国家資格合格者が、
現在では3000人以上、新設された学校の中には、すでに定員が割れて、廃校になった学校もあるというのが現状です。
その一方で、古くからある専門学校の中には、3年制の専門学校から4年制の大学にしていこうという動きもあり、現在大きな変化の真っただ中、という現状です。
しかしその大学も、偏差値で考えたら、とても医学部とは比較にならないほど低く、現状、鍼灸師の資格を取ろうと思ったら、医師や歯科医師、薬剤師等、
他の医療系国家資格と比較すれば、相対的に「簡単に」取れてしまうのが現状です。
ですので単純に学歴「のみ」で優劣を比較されたら、劣っているのは明らかです。
・・・しかし!ここで僕が個人的に言いたいのは、
「うん、だからナニ? 要はその先生が信頼できる人か、そうでないかでしょ? 学歴のみで人間性まで判断するなんて、古臭いし非常識だと思いまーす!」
です。
前回のブログで、鍼灸、東洋医学は医学であり、科学だ!ということを述べました。
西洋医学と比較しても、東洋医学そのものは何ら劣りません。
(当然、疾患や場面によっての得手不得手はあるけどね。)
ただ、実践する人の力量によって、ピンキリの世界になってしまっているのが、現代の日本の東洋医学の大きな問題だと思います。
だからこないだのような事故も後を絶たない訳です。
ちなみに余談ですが、お隣の韓国では、韓医師(鍼灸、漢方を専門に扱う、東洋医学の医師)の大学に入るのは超難関で、倍率は10倍以上、
過去には結婚したい職業No1に選ばれるほど、生活の安定した、認知度の高い職業であるのに対し、日本のこの悲惨な現状は、一体何なんでしょうか。
(苦笑・・・国民の認識も含めて、です。)
東洋医学はいいものなんだから、日本も韓国のように、最初から優秀な人しかなれないようにすればいいのに、と思いますが、そうもいかない難しいしがらみが色々とあるようです。
(でもそうになったら僕が鍼灸師になれなかったりしてネ(笑))
以前、韓国の韓医師の医院(韓医院)の国外営業部長の方が、北辰会の勉強会に見えた翌日、清明院に治療を受けにみえた時、日本の東洋医学の制度的な現状に驚き、
非常に落胆しておられました。
僕(清明院)としては、現状を憂いてばっかりいても始まりませんので、こうした逆風に負けずに、患者さんの笑顔のために、日々確かな東洋医学の実践を頑張っております!
僕なんか、学歴なんてないに等しいけど、それでもよかったら是非診させて下さい(笑)
ヤル気は最高にあります!
(こういう風に言うと、ただのバカだと思われるかな(苦笑)。)
次回は3、についてです。
読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!
清明院に皆様のお力を!<m(__)m>
清明院オフィシャルホームページ(PC)
清明院スタッフブログ『清明なる日々』
2012.07.08
2016.05.09
2016.04.12
2016.04.28
2015.06.04
2012.12.23
2014.02.17
2014.04.26
2025.04.01
2025年 4月の診療日時2025.03.13
2025年2月の活動記録2025.03.01
2025年 3月の診療日時2025.02.06
2025年1月の活動記録2025.02.01
2025年 2月の診療日時2025.01.21
順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10
2024年12月の活動記録2025.01.02
2025年 1月の診療日時2025.01.01
謹賀鍼年!!2024.12.28
年内診療終了!!2024.12.14
2024年11月の活動記録2024.12.01
2024年 12月の診療日時2024.11.07
2024年10月の活動記録2024.11.01
2024年 11月の診療日時2024.10.10
清明院15周年!!!2024.10.09
2024年9月の活動記録2024.10.01
2024年 10月の診療日時2024.09.19
2024年8月の活動記録2024.09.01
2024年 9月の診療日時2024.08.03
2024年7月の活動記録2024.08.01
2024年 8月の診療日時2024.07.10
患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05
2024年6月の活動記録2024.07.01
2024年 7月の診療日時2024.06.05
2024年5月の活動記録2024.06.01
2024年 6月の診療日時2024.05.10
2024年4月の活動記録2024.05.01
2024年 5月の診療日時2024.04.13
(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02
2024年3月の活動記録2024.04.01
2024年 4月の診療日時2024.03.14
2024年2月の活動記録2024.03.01
2024年 3月の診療日時2024.02.15
2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04
3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03
3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02
2024年1月の活動記録2024.02.01
2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01
2024年 2月の診療日時2024.01.11
2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05
診療再開!!2024.01.01
2024年 1月の診療日時2023.12.30
2023年、鍼療納め!!2023.12.21
(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01
2023年 12月の診療日時2023.11.26
患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25
患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22
12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21
今週からの講演スケジュール2023.11.16
日本東方医学会学術大会、申し込み締め切り迫る!!